生ごみ処理機は、キッチンでの生ごみ処理を衛生的かつ手軽に行える便利な家電です。しかし、毎日使用することを考えると、電気代の負担が気になるところです。
実は生ごみ処理機には熱処理式、バイオ式、ハイブリッド式の3つの方式があり、それぞれ消費電力や運転時間が異なります。また、使い方や設定によっても電気代は大きく変わってきます。
本記事では、各処理方式の特徴や電気代の目安、効率的な使用方法を詳しく解説します。生ごみ処理機を賢く使いこなし、電気代を抑えながら快適なキッチンライフを実現しましょう。
生ごみ処理機の3つの処理方式とは?

生ごみ処理機には、熱処理式(乾燥式)、バイオ式、ハイブリッド式の3つの方式があります。それぞれ処理方法が異なり、電気代にも大きな違いがあります。ここではそれぞれの特性について詳しく説明していきます。
熱処理式(乾燥式)とは?
【主な特徴】
- 高温の温風で生ごみを乾燥
- 処理時間は約2~3時間
- 消費電力は約800W
- 室内設置が可能
- コンパクトなサイズ
- 1回あたりの処理量は約1~2kg
熱処理式は、生ごみから水分を効率的に除去できるため、処理後の臭いが少なく衛生的です。キッチンに置いても場所を取らないコンパクトな設計が中心で、生ごみをためずにその都度処理できます。一方で、乾燥時には、大きな音がでます。
処理中は高温の温風を使用するため、運転時間を短くできる反面、他の方式と比べて消費電力が高く、電気代は割高になります。
バイオ式とは?
【主な特徴】
- 微生物の力で生ごみを分解
- 24時間継続運転が基本
- 消費電力は約150~170W
- 室外設置が基本
- サイズが大きめ
- 1日あたりの処理量は約2kg
バイオ式は、専用のバイオチップと生ごみを混ぜ合わせることで、自然な形で分解が進みます。処理後の生ごみは堆肥として再利用できるため、家庭菜園を楽しむ人に向いています。
消費電力は比較的低めですが、24時間稼働が基本で、定期的にバイオチップの交換が必要です。臭いが出やすく室外設置が一般的なため、設置場所の確保に注意しましょう。
ハイブリッド式とは?
【主な特徴】
- 熱処理とバイオ処理の組み合わせ
- 24時間継続運転が基本
- 消費電力は約60~90W
- 室内外両方に設置可能
- 大きめのサイズ
- 1日あたりの処理量は約1.5kg
ハイブリッド式は、熱処理とバイオ処理の長所を組み合わせた方式です。3つの方式の中で最も消費電力が少なく、処理効率も優れています。
処理後の生ごみは肥料として使用可能で、処理時の音も比較的静かです。バイオチップの交換は必要ですが、交換頻度は純粋なバイオ式より少なくて済みます。ただし、装置のサイズが大きめとなるため、設置場所の確保が必要です。
知りたい!生ごみ処理機の電気代の実態
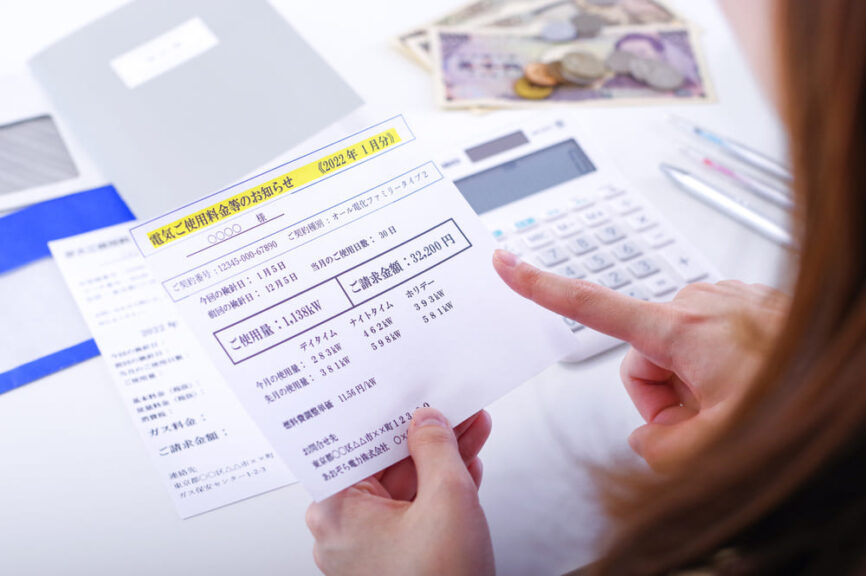
家庭で生ごみ処理機を使用する際、気になるのが毎月の電気代への影響です。処理方式によって消費電力が異なり、さらに使用頻度や生ごみの量によっても電気代は変動します。
実際の使用状況に基づいた具体的な数値を見ながら、家計への影響を考えていきましょう。
処理方式別の消費電力の違い
| 処理方式 | 消費電力 | 1日の消費電力量 |
| 熱処理式 | 600~800W | 1.2~2.4kWh |
| バイオ式 | 150~170W | 3.6~4.08kWh |
| ハイブリッド式 | 60~90W | 1.4~2.2kWh |
※熱処理式は1日1回2~3時間使用の場合
※バイオ式とハイブリッド式は24時間稼働を想定
一見すると消費電力の低さが電気代の安さにつながるように思えますが、実際の使用時間や処理能力によって、総合的な電気代は変わってきます。
熱処理式は1回の処理時間が2~3時間と短いため、消費電力は高めですが、1日の消費電力量は意外と抑えられます。反対にバイオ式は消費電力が低めに見えますが、24時間稼働のため1日の消費電力量は最も高くなります。
ハイブリッド式は消費電力、1日の消費電力量ともに最も低く抑えられていますが、サイズが大きく値段が高い傾向があります。
1ヶ月の平均的な電気代を計算してみよう
生ごみ処理機1ヶ月あたりの電気代は、「1日の消費電力量(kWh)×電気料金単価(円/kWh)×日数」で計算できます。先ほど算出した、生ごみ処理機の1日の消費電力量を使って計算した結果が、下記の表です。
| 処理方式 | 1日あたり | 1ヶ月(30日)あたり |
| 熱処理式 | 35~75円/回 | 1,050~2,250円 |
| バイオ式 | 110~130円/日 | 3,300~3,900円 |
| ハイブリッド式 | 40~70円/日 | 1,200~2,100円 |
※全国家庭電気製品公正取引協議会による目安単価を用いて、1kWhあたり31円で計算
※熱処理式は1日1回使用の場合
※バイオ式とハイブリッド式は24時間稼働を想定
これらの金額は標準的な使用量での計算であり、生ごみの量や処理頻度によって電気代は変動します。
電気代の変動要因
生ごみ処理機の電気代は、処理時間と直接的な関係があります。処理時間が長くなれば長くなるほど、消費する電力量が増加するため、1回あたりの電気代が高くなってしまうのです。例えば、通常2時間で終わる処理が3時間かかると、電気代は1.5倍になることになります。
実際は単純に1.5倍ではありませんが、処理時間を短縮することは、電気代を抑える重要なポイントであることは間違いありません。
処理時間が長くなる要因と対策をまとめました。
| 変動要因 | 対策 |
| 生ごみの水分量 | キッチンペーパーで水気を拭き取る ざるやネットで十分に水切りをする 新聞紙で包んで水分を吸収させる |
| 季節・室温の変化 | 冬場は室温の高い場所に設置 夏場は風通しの良い場所を選ぶ 直射日光の当たらない場所に設置 |
| 処理量 | 規定量を超えない 生ごみは細かく刻んで投入 処理槽に均一に広げる |
| 処理モードの選択 | 生ごみの種類に応じてモードを選択 少量の場合はエコモードを使用 夜間モードの活用 |
| 機器のメンテナンス状態 | 定期的な清掃を実施 フィルターの交換 処理槽の手入れ |
電気代を抑える!賢い使い方のポイント

生ごみ処理機の電気代は、使い方次第で大きく変わります。毎日の使用方法を少し工夫するだけでOK。基本的な使い方のコツを押さえて、賢く活用していきましょう。
まとめて処理で効率アップ!
生ごみを少量ずつ処理するよりも、ある程度まとめて処理する方が電力効率が良くなります。朝と昼の生ごみは一時的に保管し、夕食後の生ごみと一緒に処理しましょう。まとめることで、1日の運転回数も減らせます。ただし、処理機の定格容量を超えないように注意しましょう。
また、生ごみを入れる前に、水切りを十分に行うことも大切です。生ごみの約8割は水分と言われており、水切りを徹底することで処理時間を短縮でき、使用電力量を削減できます。
タイマー機能を活用した節電術
電力会社の多くが、深夜時間帯の電気料金を通常より割安く設定したプランを用意しています。そのため、タイマー機能を使って、夜間に処理を開始するように設定すれば、電力料金の安い時間帯に運転を集中させることができます。
また、処理終了後は自動で電源が切れる機種も販売されており、待機電力の削減にも役立ちます。
処理時間の賢い選び方
処理時間の設定も電気代に影響します。生ごみの種類や量に合った処理時間を選択することは節電に欠かせません。
野菜くずなど水分の多い生ごみは、標準モードよりも長めの処理時間を設定します。反対に、パンくずなど乾燥しやすい生ごみは、短めの処理時間で十分です。
無駄な電力消費を防ぐためには、生ごみの状態を見極めて必要以上の処理時間を避けるようにしましょう。
処理方式によって違う!省エネのコツ
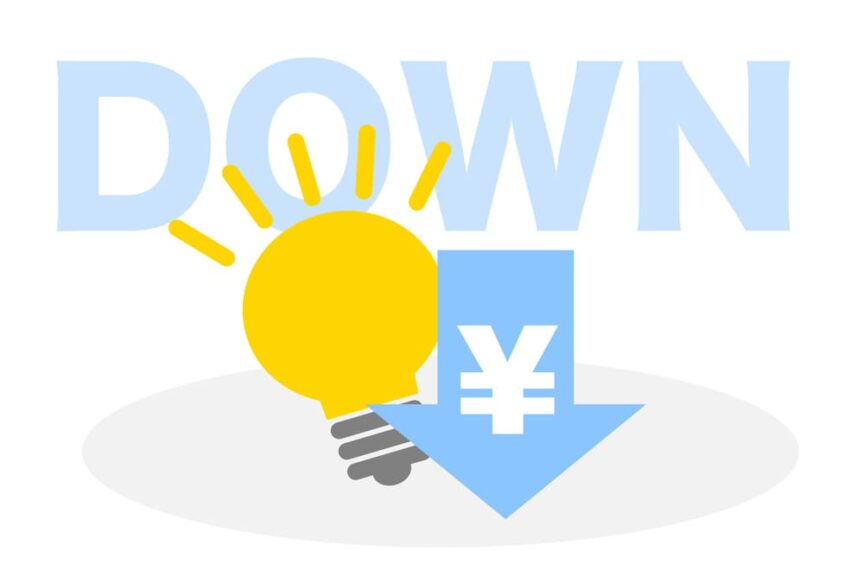
生ごみ処理機は処理方式によって特性が異なるため、それぞれに適した使い方があります。各方式の特徴を理解し、その特性に合わせて使用することが大切です。日々の使用方法を見直して、電気代の節約につなげていきましょう。
乾燥式の電力消費を抑えるテクニック
乾燥式は短時間で処理できる反面、消費電力が高めです。
生ごみは細かく切り、できるだけ平らに広げて投入します。塊になっていると乾燥ムラが生じ、処理時間が長くなってしまいます。葉物野菜など水分の多い生ごみは、新聞紙で軽く包んでから投入すると、余分な水分を吸収して処理時間を短縮できます。
処理槽の掃除も定期的に行い、熱効率の低下を防ぐようにしましょう。
バイオ式の効率的な運転方法
バイオ式は24時間稼働が基本ですが、生ごみの投入方法を工夫することで効率を上げることができます。例えば、生ごみは細かく刻んで投入し、一度に大量の生ごみを入れないようにします。また、生ごみの水分量が多すぎると微生物の活動が低下するため、事前の水切りは欠かせません。
バイオ式は、微生物の活動が活発な20~30度の環境を保つことで分解効率が高まります。冬場は室温が下がるため、保温性の高い場所への設置すると良いでしょう。
ハイブリッド式の使い分けポイント
ハイブリッド式は、乾燥とバイオ分解の両方の機能を持つため、生ごみの種類に応じた使い分けが効果的です。例えば、野菜くずなど分解しやすい生ごみはバイオ処理を主体に、魚の骨など分解しにくい生ごみは乾燥処理を主体に、と状況に応じて処理方法を選択しましょう。
処理槽内の湿度管理も重要で、水分が多すぎると乾燥に時間がかかり、少なすぎると微生物の活動が低下します。最適な状態を保つための定期的なメンテナンスを心がけましょう。
プロが教える!電気代節約の裏ワザ

生ごみ処理機を使用する際の電気代は、ちょっとした工夫で大きく変わります。専門家が実践している効率的な方法を実践して、より上手に機器を使いこなしていきましょう。
夜間電力を上手に活用するコツ
夜間電力を活用したい場合は、22時以降に処理を開始するのがおすすめです。ただし、騒音が気になる場合は、就寝前に生ごみを投入し、タイマーで深夜に処理を始めるよう設定しましょう。
時間帯別の電気料金プランを契約している場合は、23時から朝5時までの深夜時間帯に処理を集中させることで、電気代を抑えることができます。
処理開始時刻を1日の中で固定し、習慣化すると良いでしょう。
処理時間を短縮するための投入方法
処理時間を短縮するためには、生ごみの投入方法を工夫しましょう。
- 生ごみは必ず水切りを徹底
- 野菜や果物は小さめにカット
- 魚の骨や野菜の芯は細かく刻む
- 処理槽に均一に広げて投入
- 一か所に固めて入れない
処理時間に最も影響するのは水切りです。ザルやネットを使って十分に水分を切ります。キッチンペーパーで包んでから投入するのもおすすめです。
また、生ごみを小さくカットして処理槽に入れると、熱が均一に行き渡り、乾燥効率が上がります。特に処理の難しい魚の骨や野菜の芯は、できるだけ細かく刻んでから投入しましょう。
処理槽内で生ごみが一か所に固まると乾燥ムラの原因となるため、全体に均一に広げて置くことが大切です。
効率的な運転モードの使い分け
運転モードは生ごみの種類や量によって使い分けます。
葉物野菜など水分の多い生ごみは、急速モードよりも標準モードで処理する方が電力効率が良くなります。一方、パンくずなど乾燥しやすい生ごみは、短時間モードで十分な処理が可能です。処理量が少ない場合は、エコモードを活用しましょう。
季節や気温によっても最適なモードは変化するため、状況に応じた柔軟な使い分けましょう。
まとめ
生ごみ処理機は、毎日の生活を快適にする便利な家電ですが、電気代の負担を抑えるためには、処理方式の特徴を理解し、使い方を工夫することが大切です。
事前の水切りや適切な投入量の管理、夜間電力の活用など、ちょっとしたことで電気代を抑えることができます。また、生ごみの種類や量に応じて処理モードを使い分けることで、さらに効率的な運転が可能になります。
これらの節電テクニックを組み合わせることで、電気代の心配なく生ごみ処理機を活用できるでしょう。快適なキッチンライフと省エネの両立は、決して難しいことではありません。









