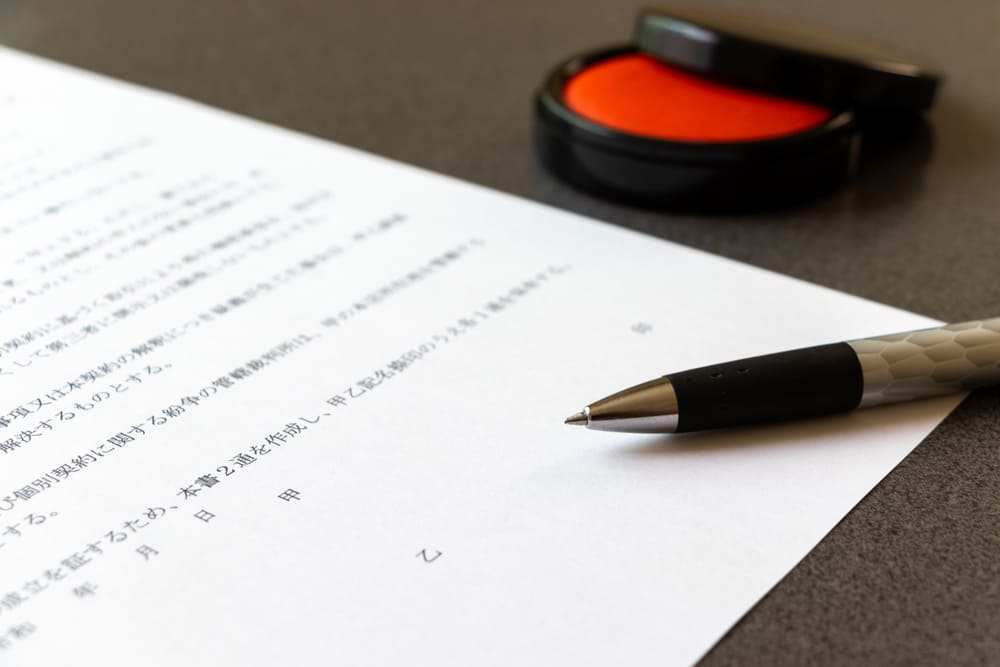資金繰りの改善策として注目されるファクタリングですが、契約時のトラブルを避けるためには正しい知識が欠かせません。ファクタリング契約では、売掛債権の譲渡や買取価格、支払条件などの重要事項を明確に理解し、契約書の細部まで確認することが大切です。
2社間と3社間の契約形態の違いや、契約締結から入金までの流れ、チェックすべき条項など、ファクタリングを安全に活用するための情報を網羅的に解説します。初めてファクタリングを検討する経営者の方も安心して取引を進めることができるでしょう。
資金調達をスムーズに行い、ビジネスの成長につなげるための実践的なガイドとしてご活用ください。
ファクタリングとは

ファクタリングは、企業が保有する売掛金や請求書をファクタリング会社などに売却して、資金を調達する金融サービスです。
大きなメリットは、通常の支払いサイクルを待たずに必要な資金をすぐに確保できる点です。資金繰りに悩む企業や、成長期にある事業者、大口取引の支払いサイクルが長い企業にとって、有効な資金調達手段となります。
ここではファクタリング契約の本質や法的位置づけ、契約形態の違いについて解説します。
ファクタリング契約とは何か
ファクタリング契約とは、企業(個人事業主)が持つ売掛債権(売掛金)を、ファクタリング会社に譲渡する契約のことです。この契約により、本来は支払期日を待たなければ回収できない売掛金を前倒しで現金化できます。
ファクタリング契約では、売掛債権譲渡(売掛債権買取)契約を結び、売掛債権の所有権と回収リスクがファクタリング会社に移ります。そのため、売掛先企業へ提供した商品やサービスの代金を受け取る権利もファクタリング会社に移ります。
契約の対価として、売掛債権額からファクタリング会社の手数料を差し引いた金額が利用者に支払われる仕組みです。
契約の法的位置づけと根拠
ファクタリング契約は、民法の債権譲渡契約(債権売買契約)に該当します。民法上、債権は譲渡可能であり、債権譲渡によって債権の移転が法的に認められています。ファクタリングは、この債権譲渡の仕組みを活用した金融取引です。
2020年の法改正により、債権譲渡禁止特約があっても債権を譲渡することが可能になり、ファクタリング取引の法的安定性が高まりました。
ただし、ファクタリングは金銭の貸付ではないため、貸金業法の適用対象外です。償還請求権を設定する場合は、実質的に金銭貸借と見なされる可能性があり、貸金業登録が必要になることがあります。
2社間契約と3社間契約の違い
ファクタリング契約には「2社間(2者間)ファクタリング」と「3社間(3者間)ファクタリング」の2種類があります。
2社間ファクタリングは、ファクタリング利用者とファクタリング会社の間だけで契約を結びます。売掛先にファクタリングの利用を知られず、スピーディーに資金調達できます。
一方、3社間ファクタリングは、利用者、ファクタリング会社、売掛先の3社で契約を結びます。この場合、売掛先からの支払いはファクタリング会社に直接行われます。2社間よりも手数料が低く設定される傾向がありますが、売掛先の承諾が必要なため、手続きに時間がかかり、資金調達までの期間が長くなります。また、売掛先企業にファクタリングの利用が知られるというデメリットも考慮する必要があります。
ファクタリング契約の全体的な流れ
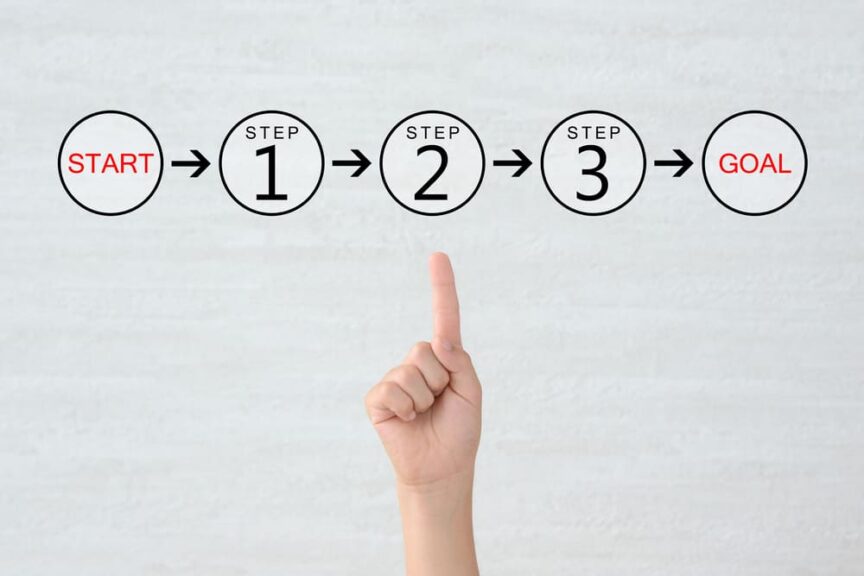
ファクタリング契約を結ぶ際には、契約がスムーズに進むよう、全体の流れを把握しておくことが大切です。問い合わせから入金までの各ステップにはポイントがあり、それらを理解しておくことで資金調達をトラブルなく行えるでしょう。
ここでは、ファクタリング契約の全体的な流れを詳しく解説します。
問い合わせ・相談から契約締結まで
ファクタリング契約の最初のステップは事前相談です。保有している売掛債権を買い取れるか、またどれくらいの手数料が発生するかなど、ファクタリング会社に相談します。複数の会社に相談し、条件を比較検討するのがおすすめです。相談後、条件に納得できれば申込みに進みます。
申込み方法はインターネット、電話、窓口、郵送などがあり、それぞれメリット・デメリットがあります。例えば、オンライン申込みは時間や場所を問わず手続きできる一方、窓口での申込みは直接相談しながら進められるため、初めての利用者に向いています。
申込み後はキャンセルが難しくなるため、契約内容を十分理解した上で進めましょう。
必要書類の準備と提出タイミング
ファクタリングの審査には、いくつかの書類が必要です。一般的に求められる書類は、下記の通りです。
- 法人登記簿謄本
- 印鑑証明書
- 身分証明書
- 決算書
- 売掛金証明書類(請求書や納品書)
- 通帳のコピー
これらの書類は申込み時または審査時に提出します。書類不足や不備があると審査に時間がかかったり、最悪の場合は否決されたりすることもあります。事前相談の際に必要書類を確認し、早めに準備しておくとスムーズです。特に印鑑証明書や登記簿謄本など、発行に時間がかかる公的書類は余裕を持って準備しましょう。
審査プロセスと通過のポイント
ファクタリングの審査では、提出した書類と(必要に応じて行われる)ヒアリングにより、ファクタリング利用の可否が判断されます。主に以下の4項目がチェックされます。
- 自社の事業内容
- ファクタリングを利用する理由
- 売掛先の事業内容や取引状況
- 売掛先のファクタリング利用に関する承諾(3社間ファクタリングの場合)
審査では売掛債権の質や存在の確実性、売掛先企業の支払能力などが評価されます。虚偽の申告や情報の隠蔽は避け、誠実に対応することが審査通過のポイントです。
なお、審査期間は数日から1週間程度が一般的ですが、ファクタリング会社や案件によって異なります。
契約締結から入金までの流れ
審査通過後、ファクタリング契約の締結に進みます。契約締結時は、契約書の内容を隅々まで確認し、不明点があれば必ず質問しましょう。契約内容に納得したら署名・押印を行います。契約書は通常2通作成し、双方で1通ずつ保管します。1通しか作成しない場合は、必ずコピーをもらうようにしてください。
契約締結後、売掛債権の額面から手数料を差し引いた金額が指定口座に入金されます。入金のタイミングは即日から数日後までファクタリング会社によって異なります。入金後、3社間ファクタリングの場合は売掛先から直接ファクタリング会社に支払いが行われます。2社間ファクタリングの場合は、売掛金を回収した後、ファクタリング会社に送金します。
契約前に確認すべき重要事項

売掛債権の条件、買取価格、支払条件など、契約の核となる部分を事前にしっかりと理解しておくことで、スムーズな取引が可能になります。逆に、これらの確認を怠ると、後々思わぬトラブルに発展する可能性があります。
ここでは、契約前に特に注意して確認すべき事項について解説します。
買取対象となる売掛債権の条件
ファクタリング会社が買取可能な売掛債権には一定の条件があります。一般的に、商品の納品や検品が終わり、支払いが確実に行われる予定の確定債権が対象です。未確定の債権や、支払期日が既に過ぎている債権は買取対象外となることが多いため、注意しましょう。
また、売掛先の信用状況も重要です。売掛先の業績不振や支払い遅延履歴がある場合、買取を断られるか、高い手数料を設定されることがあります。取引実績が浅い場合や、債権の支払期日までの期間が短すぎる・長すぎる場合なども、買取条件に影響するため確認が必要です。
債権の金額には上限・下限が設けられており、ファクタリング会社によって対応可能な金額は異なります。
買取価格(手数料率)の決定要素
ファクタリングの手数料率は、売掛債権の額面に対する割合で設定されます。手数料率は2社間ファクタリングで10~20%程度、3社間ファクタリングで1〜9%程度が相場です。これらの手数料率は、売掛先の信用力、債権の支払期日までの期間、債権金額の大きさなどによって変動します。
手数料率を決定する主な要素には、売掛先の信用リスク(倒産リスクなど)、債権回収にかかるコスト、取引の継続性などがあります。優良企業への売掛債権ほど手数料は低く設定される傾向にあります。また、継続的に取引がある場合は、単発の取引よりも手数料が優遇されることがあります。
支払条件と入金方法の選択肢
支払条件には、即日払いや数日後払いなど複数の選択肢があることが一般的です。即日払いを選択すると追加手数料が発生するケースもあるため、資金の緊急性を考慮して選択しましょう。
入金方法については、銀行振込が一般的ですが、振込手数料の負担者がファクタリング会社側か利用者側かは、確認しておきましょう。
また、分割払いを選択できるファクタリング会社もあります。この場合、一部を即時に受け取り、残りを売掛金の回収後に受け取ります。緊急性が低い場合はこうした選択肢も視野に入れると、全体の手数料負担を軽減できる可能性があります。
契約書に必ず含まれる主要条項

ファクタリング契約書には、取引を法的に保護するための様々な条項が含まれています。専門的な法律用語が使われていることも多く、理解が難しい場合もありますが、主要な条項の意味と役割を把握しておくことで、契約内容を正確に理解することができます。
ここでは、ファクタリング契約書に必ず含まれる主要条項について解説します。
売買の対象となる債権の明確な特定
ファクタリング契約書では、まず譲渡対象となる債権を明確に特定します。「いつ販売された」「いくらの商品」が対象なのか具体的に記載されます。通常、債権者(売主)、債務者(買主)の詳細情報、債権額、支払期日、債権発生の原因取引(商品・サービスの内容)などが明記されています。
この特定は非常に重要で、対象債権の情報(金額や日付など)に誤りがあると、後々トラブルの原因になります。特に複数の売掛債権がある場合は、どの債権が譲渡対象となるのかを明確にしておく必要があります。契約前に、これらの情報が正確であるかを必ず確認しましょう。不明確な部分があれば、契約締結前にファクタリング会社に質問し明確にします。
債権譲渡の方法と効力発生時期
契約書には債権譲渡の方法と効力発生時期についても明記されています。
債権譲渡の方法としては、「債権譲渡通知を行うか」「債権譲渡登記を行うか」がポイントです。これらは「対抗要件」と呼ばれ、第三者に対して債権譲渡の事実を主張するために必要な手続きです。
債権譲渡の効力発生時期も明確に規定されます。一般的には契約締結と同時に効力が発生しますが、一定の条件(例:買取代金の支払い完了時)を満たした時点で効力が発生すると定められていることもあります。
また、債権譲渡の対抗要件(通知や登記)が整うまで効力を留保する条項が含まれている場合もあります。これらの条項は債権の二重譲渡などのリスクに関わるため、内容をしっかり確認しましょう
買取価格と支払方法の詳細規定
契約書には買取価格(譲渡額)と支払方法についての詳細が記載されています。
買取価格は通常、債権額面から手数料を差し引いた金額です。手数料の計算方法(定率方式か定額方式か)や、追加費用(債権譲渡登記費用、振込手数料など)の負担についても明記されているか、確認しましょう。
支払方法については、支払時期(即日払いか数日後払いか)、支払手段(銀行振込が一般的)、支払い条件(一括払いか分割払いか)などが記載されます。また、支払いの前提条件として「必要書類の提出完了」や「対抗要件の具備」などが条件として載っていることもあります。
これらの条件を満たさない場合、支払いが遅延する可能性があるため、事前の確認は欠かせません。
表明保証条項の意味と重要性
表明保証条項とは、契約当事者が相手方に対して一定の事実を表明し、その真実性を保証する条項です。ファクタリング契約においては、「対象債権が有効に存在すること」「債権に瑕疵がないこと」「譲渡禁止特約に違反していないこと」などについて利用者側が表明保証を行います。
この条項は、万が一表明保証した内容が事実と異なっていた場合(例:債権が実際には存在しなかった)、利用者に損害賠償責任が発生することを意味します。
虚偽の表明は重大な契約違反であり、契約解除や損害賠償請求の対象となる可能性があります。そのため、表明保証の内容を十分理解し、事実と異なる点がないか確認しましょう。特に「債権の存在」「二重譲渡の不存在」は重要です。
契約形態別のチェックポイント

ファクタリングは、契約形態によって重視すべき条項や注意点が異なるため、自社が選択する契約形態に合わせた確認が必要です。ここでは、契約形態別の重要なチェックポイントについて解説します。
2社間ファクタリング契約の特有条項
2社間ファクタリング契約は、利用者とファクタリング会社の間でのみ契約が締結されるため、特有条項があります。
まず確認すべきは「業務委託契約」の有無です。2社間ファクタリングでは、債権譲渡後も利用者が売掛先から回収を行うため、この回収業務を委託する契約が別途必要です。
債権譲渡通知の扱いも重要なポイントです。2社間ファクタリングでは通常、売掛先に知られないよう債権譲渡通知は行いませんが、多くの契約書には「債権譲渡通知を留保する」という条項が含まれています。これは、必要に応じてファクタリング会社が債権譲渡通知を送付できる権利を留保するものです。
3社間ファクタリング契約の重要ポイント
3社間ファクタリング契約では、利用者、ファクタリング会社、売掛先の3者が関与するため、2社間とは確認すべきポイントが異なります。
最も重要なのは「売掛先の承諾」に関する条項です。3社間ファクタリングでは、売掛先が債権譲渡を承諾し、ファクタリング会社への支払いを約束することが前提となります。この承諾がなければ契約は成立しません。
次は、支払先変更の手続きに関する条項です。売掛先は支払先をファクタリング会社に変更する必要があるため、その手続きの詳細(通知方法、期限など)が契約書に明記されているはずです。さらに、売掛先が支払いを拒否した場合の対応についても規定されているか確認しましょう。
スポット取引型契約の確認事項
スポット取引型のファクタリング契約は、1回限りの取引として締結されるものです。継続的な契約と異なり、特定の売掛債権のみを対象とするため、確認すべきポイントが異なります。
まず、契約期間が明確に1回限りであるか確認しましょう。中には自動更新条項が含まれていることもあり、意図せず継続契約となる場合があります。
対象債権の特定が明確かつ正確であるかも確認が必要です。スポット取引では特定の債権のみが対象となるため、その特定が曖昧だとトラブルの原因になります。債権金額、支払期日、債務者情報などが正確に記載されているか確認してください。
さらに、契約終了条件も確認すべきポイントです。
契約書の細部にわたるチェックリスト

ファクタリング契約書には、主要条項に加えて様々な細部条項が含まれています。これらの細部条項は一見些細に見えても、トラブル発生時に意味を持つことがあります。契約書を読む際は、大枠だけでなく細部まで注意深くチェックしましょう。
専門的な法律用語で記載されていることも多いため、分からない点はファクタリング会社に質問し、疑問を残さないことが大切です。
債権譲渡の対抗要件に関する条項
債権譲渡の対抗要件とは、債権が譲渡されたことを第三者に主張するための要件です。対抗要件には「債務者対抗要件」と「第三者対抗要件」の2種類があります。
- 債務者対抗要件:売掛先に対して債権譲渡の効力を主張するための要件で、通常は債権譲渡通知または債権譲渡承諾に記載される
- 第三者対抗要件:他の第三者(他のファクタリング会社など)に対して債権譲渡の効力を主張するための要件で、債権譲渡登記または確定日付のある通知・承諾によって成立
契約書ではこれらの対抗要件をどのように満たすか、その方法と時期、費用負担についての条項が含まれます。
遡及(さかのぼり)条項の有無と範囲
遡及条項とは、売掛先が支払いを行わなかった場合などに、ファクタリング会社が利用者に対して売掛債権の買戻しを要求できる条項です。これは「償還請求権」とも呼ばれ、リコース(遡及型)ファクタリングの特徴です。通常、ファクタリングはノンリコース(非遡及型)であるべきですが、契約によってはリコース条項が含まれていることがあります。
契約書で遡及条項の有無を確認し、含まれている場合はその範囲(どのような場合に買戻し義務が生じるか)を確認します。例えば、売掛先の倒産時のみなのか、単なる支払遅延の場合も含まれるのかなど、条件は様々です。遡及条項が広範囲に設定されていると、利用者にとって大きなリスクとなります。
譲渡禁止特約がある場合の対応
譲渡禁止特約とは、債権(売掛金)を第三者に譲渡することを禁止する特約です。売掛先との基本契約に譲渡禁止特約が含まれている場合、原則としてその債権をファクタリングの対象とすることはできません。しかし、2020年の民法改正により、譲渡禁止特約があっても債権譲渡自体は有効とされるようになりました。
ただし、譲渡禁止特約に違反した場合、売掛先との契約違反となる可能性があります。ファクタリング契約書では、譲渡禁止特約の有無についての表明保証条項や、譲渡禁止特約がある場合の対応(売掛先の承諾取得など)について規定されているはずです。
期限の利益喪失条項の確認
期限の利益喪失条項とは、契約違反などの一定の事由が発生した場合に、期限の利益(支払期限まで支払いを猶予される利益)を失い、即時に債務の履行義務が生じる条項です。ファクタリング契約では、利用者が契約上の義務に違反した場合などに、ファクタリング会社が期限の利益を喪失させる権利を保有することがあります。
この条項は、どのような場合に期限の利益が喪失するのか、その具体的な事由と効果を確認しましょう。多くは、虚偽の表明保証をした場合、売掛金を回収したのに送金しなかった場合などが含まれています。期限の利益を喪失すると、即時に損害賠償義務が生じるなど深刻な影響があります。
電子契約と紙の契約書の違い

近年、ファクタリング契約においても電子契約の利用が増えています。電子契約は時間や場所の制約なく契約を締結できる利便性がありますが、紙の契約書とは異なる特徴や注意点があります。
ここでは、電子契約と紙の契約書の違いについて解説し、それぞれのメリットとデメリットを明らかにします。
電子契約の法的有効性と利便性
電子契約は、2001年に施行された「電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)」により、一定の条件を満たせば紙の契約書と同等の法的効力を持つことが認められています。電子署名が付されたデータは、本人作成の推定効が働くため、紙の契約書に実印を押印したのと同様の効力を持ちます。
電子契約の最大のメリットは利便性の高さです。時間や場所を選ばず契約が締結でき、郵送や対面での手続きが不要なため、契約締結までの時間を大幅に短縮できます。また、契約書の保管や管理も電子的に行えるため、紛失のリスクが低く、検索性にも優れています。印紙税が不要になるというコスト面での利点もあります。
電子署名・電子認証の仕組みと安全性
電子契約の核となるのは電子署名と電子認証です。電子署名は、データの作成者を証明し、データが改ざんされていないことを保証する技術で、公開鍵暗号方式などの暗号技術を用いており、高い安全性を持っています。電子認証は、電子署名が確かに本人のものであることを第三者機関が証明する仕組みです。
電子契約の安全性は、使用される電子署名・電子認証のレベルによって変わります。一般的には、特定認証業務の認定を受けた認証局が発行する「電子証明書」を用いた電子署名が最も安全とされています。
書面契約ならではの安心感と特徴
紙の契約書(書面契約)は従来から用いられてきた方法で、当事者が対面で契約内容を確認し、署名・押印を行います。書面契約の最大の特徴は、当事者同士が直接顔を合わせることで生まれる信頼感と安心感です。特に初めての取引先との契約では、この点が重視されることがあります。
電子契約ではメールやチャットでのやり取りになるため、微妙なニュアンスが伝わりにくいことがありますが、書面契約では契約書の細部について直接質問し、その場で修正や確認が可能です。また、高齢者など電子機器の操作に不慣れな方にとっては、書面契約のほうが安心して契約を進められるというメリットもあります。
契約上のトラブルを防ぐためのポイント

ファクタリング契約においては、様々なトラブルが発生する可能性があります。ここでは、ファクタリング契約上のトラブルを防ぐためのポイントについて解説します。これらのポイントを押さえることで、スムーズな取引と良好な関係を維持することができるでしょう。
契約条件の明確な理解と文書化
ファクタリング契約におけるトラブルの多くは、契約条件の理解不足や認識の相違から発生します。トラブルを防ぐためには、契約条件を明確に理解し、重要な事項は必ず文書化することが大切です。特に手数料率、支払条件、債権回収方法などの核心部分は、口頭での合意だけでなく必ず契約書に明記してもらいましょう。
契約書の内容で不明な点がある場合は、その場で質問し明確にします。専門用語や法律用語が多用されていても、遠慮せずに説明を求めましょう。また、契約前の見積もりや提案内容と、実際の契約書の内容に相違がないかも確認します。
取引先への適切な説明と協力体制
3社間ファクタリングの場合、売掛先の協力が不可欠です。トラブルを防ぐためには、売掛先に対してファクタリングの仕組みと必要性を説明し、理解と協力を得ることが欠かせません。特に支払先の変更や債権譲渡承諾書の提出など、売掛先に負担がかかる手続きについては、事前に丁寧に説明しましょう。
また、売掛先との良好な関係を維持するためには、ファクタリング会社と売掛先とのコミュニケーションにも気を配ります。ファクタリング会社の担当者が売掛先にどのように接するか、どのようなタイミングで連絡するかなどについても、事前に確認しておくと良いでしょう。
支払遅延リスクへの事前対策
売掛先からの支払遅延は、ファクタリング契約におけるトラブルの一因です。特に2社間ファクタリングの場合、利用者が売掛先から回収した売掛金をファクタリング会社に送金する義務があるため、売掛先の支払遅延が直接的に影響します。このリスクに対しては、事前の対策が重要です。
まず、売掛先の支払能力や過去の支払実績を正確に把握し、ファクタリング会社に共有します。特に支払遅延の履歴がある売掛先については、その事実を隠さずに伝えるべきです。
また、契約書に支払遅延時の対応(猶予期間の有無、延滞金の計算方法など)が明記されているか確認しましょう。
まとめ
ファクタリング契約は売掛債権を活用した効果的な資金調達手段ですが、契約内容をしっかり理解し、細部まで確認することが成功の鍵となります。2社間と3社間の契約形態の違いを理解し、自社に最適な方法を選択しましょう。
契約前の準備から書類の確認、審査対策、そして契約書のチェックポイントを押さえることで、不測のトラブルを回避できます。特に償還請求権の有無や債権譲渡の方法、遡及条項など、細部の条項にも注意を払います。
信頼できるファクタリング会社を選び、契約条件を明確に理解することで、資金調達をスムーズに行い、ビジネスの成長を加速させることができるでしょう。