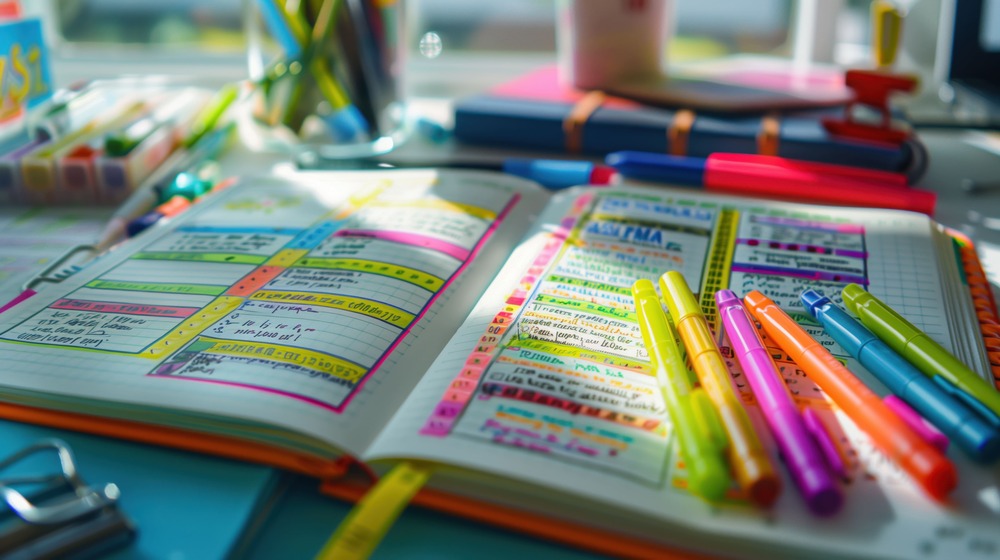売掛金を早期に現金化できるファクタリングは、銀行融資に比べて審査が柔軟で、迅速な資金調達が可能であることから、事業資金の調達方法として近年注目を集めています。しかし、ファクタリングを利用する際には適切な会計処理が欠かせません。
ファクタリングには「保証型」と「買取型」の2種類あります。買取型には「2社間」と「3社間」の取引形態があり、それぞれで仕訳方法が異なります。企業の財務状況を適切に把握するために、正確な会計処理をしましょう。
本記事では、ファクタリングの基本から各種類における仕訳の方法、注意すべきポイントまで、経理担当者が知っておくべき情報を分かりやすく解説していきます。
ファクタリングの基本とは?

事業資金の調達方法として注目されているのがファクタリングです。売掛金を早期に現金化できる仕組みとして多くの企業に利用されています。その歴史的背景や融資との違いを理解することで、より効果的な活用ができるでしょう。
ファクタリングの起源
売掛債権を現金化する金融サービスであるファクタリングは、数百年もの歴史があります。
中世のイギリスで始まり、その後アメリカへと広がりました。日本では1970年代にようやく知られるようになりましたが、当時は商慣習との相性の問題からあまり普及しませんでした。
転機となったのは法改正により債権譲渡がしやすくなった時期です。インターネット技術の発展によって、ファクタリングサービスの提供が容易になり、個人事業主を含む中小事業者にとっても現実的な資金管理の選択肢となりました。
現在ではオンラインで申し込みから資金のやり取りまですべてが完結するサービスや、AIを活用した与信審査により迅速に資金を提供するサービスも登場しています。このように、ファクタリングは古くから存在する金融手法でありながら、技術革新によって現代のビジネスニーズに合わせた形で進化し続けています。
ファクタリングと融資の違いとは?
銀行融資とファクタリングは、どちらも資金調達の手段ですが、その性質には大きな違いがあります。
融資は借入金として負債に計上されますが、ファクタリングは売掛金の売却であり、債務ではありません。
| 項目 | ファクタリング | 融資 |
|---|---|---|
| 性質 | 売掛債権の売却 | 借入金(負債) |
| 貸借対照表への影響 | 負債が増えない | 負債が増える |
| 資金調達スピード | 最短即日可能 | 数週間〜数ヶ月 |
| 審査の中心 | 売掛先の信用力 | 自社の信用力 |
| 金利・手数料 | 手数料(2%〜18%) | 金利(年率1%〜10%) |
| 返済方法 | 返済なし | 元本と利息の返済が必要 |
| 担保・保証人 | 原則不要 | 必要な場合が多い |
| 向いている場面 | 短期的な資金需要急な支払い対応 | 設備投資など長期資金低コストでの調達 |
事業の状況や資金調達の目的に応じて、両者を使い分けることで効果的な資金繰り改善ができます。
会計処理におけるファクタリングの種類とは?
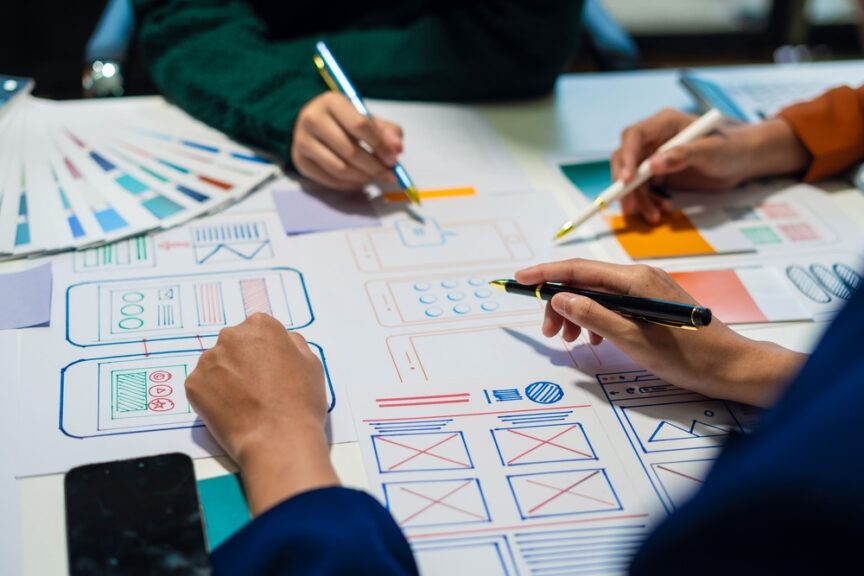
ファクタリングには主に「保証型」と「買取型」の2種類があります。利用する種類によって会計処理の方法が異なるため、それぞれの特性を理解して正確な会計処理をしましょう。
保証型ファクタリング
保証型ファクタリングは、売掛債権の回収不能リスクを軽減するためのサービスです。取引先が倒産するなどして売掛金が回収できなくなった場合に、ファクタリング会社から保証金が支払われる仕組みです。掛け捨て保険に似た性質を持ち、大口の売掛先との取引で貸し倒れリスクを回避したい場合に活用されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 貸倒れリスクの軽減 |
| 対象 | 特定の売掛先との取引 |
| 手数料 | 保証料(取引先の信用度により変動) |
| 資金化タイミング | 通常の支払期日もしくは売掛金回収不能確定時 |
| 主な勘定科目 | 支払手数料、貸倒損失、雑収入 |
| 向いている企業 | 大口取引先に依存している企業取引先の支払能力に不安がある企業貸倒れによる資金ショックを避けたい企業 |
| 注意点 | 売掛先の信用調査が行われる資金調達目的には向かない保証範囲に制限がある場合がある |
買取型ファクタリング
買取型ファクタリングは、売掛債権をファクタリング会社に譲渡して早期に現金化するサービスです。通常の支払期日を待たずに資金を調達できるため、資金繰りの改善に役立ちます。
| 項目 | 2社間ファクタリング | 3社間ファクタリング |
|---|---|---|
| 契約当事者 | 利用者とファクタリング会社 | 利用者、売掛先、ファクタリング会社 |
| 売掛先への通知 | 不要 | 必要(承諾が必要) |
| 手数料相場 | 比較的高い(8〜18%程度) | 比較的低い(2〜9%程度) |
| 資金化スピード | 最短即日可能 | 数日〜1週間程度 |
| 入金の流れ | 売掛先→利用者→ファクタリング会社 | 売掛先→ファクタリング会社 |
| 主な勘定科目 | 未収入金、売上債権売却損、預り金 | 未収入金、売上債権売却損 |
| 向いている企業 | 急な資金需要がある企業取引先との関係を優先したい企業即日の資金調達を望む企業 | 手数料を抑えたい企業取引先の承諾が得られる企業計画的な資金調達を行う企業 |
| 注意点 | 手数料が高い売掛先からの入金後にファクタリング会社への支払いが必要 | 売掛先に資金調達の事実が知られる承諾手続きに時間がかかる |
ファクタリングの仕訳と勘定科目の重要性

ファクタリングを利用する際には、正確な会計処理が不可欠です。特に保証料の計上や売掛金の入金処理、万が一の回収不能時の処理など、それぞれの場面で適切な勘定科目を用いた仕訳が必要になります。
保証料の計上と勘定科目
保証型ファクタリングを利用する際、最初に発生するのが保証料の支払いです。この保証料は、ファクタリング契約が結ばれた時点で発生し、実際の入金の有無にかかわらず支払う必要があります。会計処理としては、「支払手数料」という勘定科目を使用します。
この処理によって、保証料が経費として計上され、事業の収支計算に反映されます。保証料の金額はファクタリング会社によって異なり、取引先の信用状況によって変動します。一般的に信用度の高い大企業との取引の場合は保証料が低く設定されますが、実績の少ないスタートアップとの取引では高めに設定される場合もあります。
売掛金の入金処理と勘定科目
売掛金が発生した時点では、まず通常の会計処理と同様に「売掛金」と「売上」を計上します。
これにより、売掛金の残高がゼロになり、入金が完了したことが会計上も明確になります。銀行振込で入金された場合は「現金」ではなく「普通預金」として処理するのが一般的です。
特に保証型ファクタリングを利用している場合、売掛金が問題なく回収できれば、追加で発生するのは保証料の支払いのみなので、入金処理自体は通常の取引と同じ流れになります。このように、売掛金の入金処理は基本的な会計処理ですが、ファクタリングの種類によって後続の処理が変わってくるため注意が必要です。
売掛金回収不能時の処理と勘定科目
取引先の倒産などにより売掛金が回収できなくなった場合、まず「貸倒損失」として処理します。
これにより、回収できない売掛金が会計上は消去されます。保証型ファクタリングを利用していれば、次にファクタリング会社から保証金が支払われるため、その処理も必要になります。
この「雑収入」は、本業以外の収入で金額が小さいものを処理する勘定科目です。こうした一連の処理によって、売掛金が回収できなくなるというリスクが顕在化しても、保証型ファクタリングによって資金的な損失を最小限に抑えられることが会計上も明確になります。売掛金の回収不能は企業経営にとって大きなリスクですが、適切なファクタリングの活用と正確な会計処理によって、そのリスクを管理することができます。
買取型ファクタリングの会計処理と勘定科目

買取型ファクタリングには2社間と3社間の形態があり、それぞれで会計処理の方法に違いがあります。正確な仕訳を行うためには、取引の各段階における適切な勘定科目を選択しましょう。
2社間ファクタリングの取引処理と科目
2社間ファクタリングは、ファクタリング利用者とファクタリング会社の間で行われる取引です。売掛先に知られることなく資金調達ができる点が特徴です。この形態での会計処理は、売掛金の発生から始まり、ファクタリング契約、入金、さらに売掛先からの入金とファクタリング会社への支払いまで、複数のステップで行う必要があります。
売掛金が発生した場合
商品やサービスを販売して、後日入金される取引を行った場合、まず売掛金の発生を記録します。
この時点では通常の販売取引と同じ会計処理となります。売掛金は流動資産の一つとして貸借対照表に計上され、将来的に現金化される予定の資産として扱われます。この基本的な仕訳はその後のファクタリングの処理の基礎となるもので、後続のファクタリング処理を円滑に進めるための第一歩といえるでしょう。
ファクタリングを契約した場合
ファクタリング契約を締結したら、売掛金を「未収入金」に振り替えます。
「未収入金」とは、営業活動以外の取引で発生した債権や、資産を売却した代金が後で入金される場合に用いる勘定科目です。ファクタリングは売掛金の売却取引であるため、この科目を使用します。この処理により、売掛金は会計上消去され、未収入金としてファクタリング会社からの入金を待つ状態になります。
ファクタリング契約と入金が同時の場合
特に2社間ファクタリングでは、契約締結と同時に入金されるケースがあります。この場合、「未収入金」を経由せずに直接処理することが可能です。
これにより、売掛金が消去され、実際に入金された金額と手数料の差額が「売上債権売却損」として明示されます。この処理方法はシンプルで、契約から入金までの流れが迅速な場合に適しています。
売掛金が入金された場合
売掛金は通常の支払期日に売掛先から利用者に入金されますが、2社間ファクタリングではすでにファクタリング会社から前払いで資金を受け取っているため、この入金はファクタリング会社へ渡すためのものとなります。
ここでの「預り金」は、一時的にファクタリング会社のために預かっているお金を示します。この仕訳によって、売掛先から入金されたお金はファクタリング会社へ支払うべきものであることが明確になります。
3社間ファクタリングの記帳方法と科目
3社間ファクタリングでは、利用者、ファクタリング会社、売掛先の3社が関与する取引形態となります。売掛先への通知と承諾が必要なため手続きが増えますが、リスクが低いため手数料が安くなる傾向があります。この形態での会計処理は2社間と一部異なるため、適切な記帳方法を理解しましょう。
売掛金が発生した場合
3社間ファクタリングでも、まずは通常の取引と同様に売掛金の発生を記録します。
この基本的な仕訳は2社間ファクタリングと同じであり、どのような形態のファクタリングを利用するにしても、最初の売掛金計上は共通です。
ファクタリングを契約した場合
3社間ファクタリングでも、ファクタリング契約を締結したら売掛金を「未収入金」に振り替えます。
この処理は2社間ファクタリングと同じですが、3社間ファクタリングでは売掛先の承諾を得る手続きが加わるため、契約から入金までの期間が長くなりやすい傾向があります。そのため、この未収入金への振替は3社間ファクタリングでは重要な処理になります。
売掛金が入金された場合
3社間ファクタリングの大きな特徴は、売掛先がファクタリング会社に直接支払う点です。そのため、2社間ファクタリングで必要だった「売掛先からの入金処理」や「ファクタリング会社への支払い処理」は発生しません。3社間ファクタリングでの入金処理は、ファクタリング会社から利用者への入金処理のみとなります。
この処理により、未収入金が消去され、実際に入金された金額と手数料の差額が「売上債権売却損」として計上されます。3社間ファクタリングでは会計処理のステップが少なくなるため、記帳作業自体は2社間よりも簡略化されますが、売掛先との調整など実務面での手間が増える点は考慮する必要があります。
ファクタリングの仕訳で悩んだら相談すべき先

ファクタリングの会計処理に不安や疑問を感じたら、専門家に相談することが解決への近道です。税理士をはじめ、税務署や各種団体など、頼れる相談先について知っておくことで、正確な会計処理を実現できます。
税理士
会計や税務の専門家である税理士は、ファクタリングの仕訳に関する最も信頼できる相談先です。税理士は最新の税法改正にも精通しており、ファクタリングの複雑な会計処理について適切なアドバイスを提供してくれます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 相談できる内容 | ファクタリングの会計処理全般 勘定科目の選択税務上の取り扱い 節税対策 決算対策 |
| メリット | 専門的な知識に基づく正確なアドバイス 個別の事業状況に合わせた提案 最新の税法改正情報の提供 税務調査対応のサポート |
| デメリット | 顧問契約の場合は費用が発生(月額数万円〜) スポット相談でも費用がかかることが多い |
| 活用方法 | 定期的な顧問契約を結ぶ 特定の問題が発生した際のスポット相談 確定申告時の相談 |
| 向いている企業 | 財務状況が複雑な中小企業 ファクタリングを頻繁に利用する企業 経理担当者が不在または経験が浅い企業 |
特にファクタリングは比較的新しい金融サービスであり、一般的な経理担当者にとっては馴染みが薄いことも多いため、専門家のサポートが効果的です。税理士は単なる会計処理の助言者ではなく、事業の財務戦略を考える上でのパートナーとなるため、長期的な関係構築が望ましいでしょう。
税務署
最寄りの税務署も、ファクタリングの会計処理に関する疑問を解決するための相談先として活用できます。特に個人課税部門(記帳指導担当)では、確定申告の相談や青色申告の記帳指導などを行っています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 相談できる内容 | 基本的な記帳方法 勘定科目の選択 消費税の取り扱い 確定申告関連の質問 |
| メリット | 無料で相談可能 公的機関からの回答で安心感がある 記帳に関する説明会も開催 税法解釈の公式見解が得られる |
| デメリット | 混雑時は待ち時間が長い 個別の経営相談まではできない 基本的な内容が中心 |
| 活用方法 | 記帳説明会への参加 基本的な疑問の相談 確定申告時期の相談 |
| 向いている企業 | 個人事業主 小規模企業 基本的な会計処理を学びたい方 |
税務署は納税者をサポートするための機関なので、遠慮せずに活用しましょう。基本的な仕訳方法や税務上の取り扱いについての疑問は、多くが税務署で解決できます。また、税務署からの回答は税法解釈の公的な見解となるため、安心感があります。
納税協会
納税協会は、税に関する事業を広く行い、適切な税金の申告と納税を推進している公益社団法人です。小規模事業者の会員を対象に記帳指導を行っているため、ファクタリングの仕訳に関する質問もできます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 相談できる内容 | 記帳指導 簿記の基礎知識 税に関する質問 ファクタリングの会計処理 |
| メリット | 会費が比較的安価(年間数千円程度) 税知識普及のための説明会開催 税理士による簿記教室 会員同士の情報交換の場 |
| デメリット | 大阪を中心とした関西圏が主な活動エリア 地域によってサービス内容に差がある |
| 活用方法 | 各種説明会への参加 記帳指導の利用 会員になって定期的に相談 |
| 向いている企業 | 関西圏の個人事業主 小規模企業 費用を抑えて相談したい方 |
納税協会の会費は地域の納税協会によって異なりますが、年間数千円程度が目安で、税理士と顧問契約を結ぶよりもはるかに費用を抑えられるメリットがあります。ただし、納税協会は大阪を中心とした関西の府県(大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県)で主に活動しているため、これらの地域で事業を行っている方に適した選択肢といえるでしょう。
商工会議所や商工会
商工会議所や商工会も、ファクタリングの会計処理に関する相談先として活用できます。これらの組織は地域の事業や事業者のコミュニティをサポートすることを目的としており、中小企業や個人事業主に対して多様なサービスを提供しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 相談できる内容 | 経理に関する基本的な質問 帳簿のつけ方 ファクタリングを含む資金調達の相談 経営全般の相談 |
| メリット | 会費が比較的安価 地域に密着したサポート 経営相談も同時に可能 同業者との情報交換の場 全国各地に存在するためアクセスしやすい |
| デメリット | 税理士のような専門的なアドバイスは限定的 地域によってサービス内容に差がある |
| 活用方法 | 経営相談の一環として会計処理を相談 セミナーや勉強会への参加 会員になって定期的に相談 |
| 向いている企業 | 地域密着型の中小企業 個人事業主 経営全般の相談もしたい方 |
商工会議所や商工会の大きな特徴は、同じ地域の事業者と情報の交換ができることです。全国各地に存在するため、アクセスしやすいのも利点で、地域に根ざした事業支援機関として、会計処理に限らず幅広い経営課題の相談先となるでしょう。
ファクタリングの仕訳に注意すべきポイント

ファクタリングの会計処理には、いくつか注意すべきポイントがあります。手数料の処理や消費税の取り扱い、決算期をまたぐ場合の影響など、これらを正しく理解することで、トラブルを未然に防ぎ、適切な会計処理が可能です。
手数料と売上債権売却損の関連性
ファクタリングを利用する際、最も注意すべき点の一つが手数料の処理方法です。買取型ファクタリングの場合、ファクタリング会社に支払う手数料は「売上債権売却損」として処理するのが基本です。これは、売掛金の金額に対して実際に受け取る金額との差額が損失として発生するためです。
手数料と売上債権売却損に関する重要ポイント
- 買取型ファクタリングの手数料は「売上債権売却損」で計上するのが原則
- 売上債権売却損は損益計算書上の費用として扱われる
- 会計ソフトによっては「売上債権売却損」の項目がない場合がある
- その場合は「雑損失」「支払手数料」「割引料」などの勘定科目で代用可能
- 手数料は事業運営のコストとして適切に計上すべき
手数料率はファクタリング会社によって異なるため、複数の会社から見積もりを取り、比較や検討をすることが賢明です。適切な勘定科目で正確に計上することで、事業の財務状況を正しく把握できます。
ファクタリングにおける消費税の取り扱い
ファクタリング取引は「金銭債権の譲渡」に該当するため、消費税法上の非課税取引となります。つまり、ファクタリングの取引金額や手数料には消費税がかからないのです。
消費税に関する注意点
- ファクタリング取引(債権譲渡)自体は非課税取引
- 売掛金の原取引(商品販売など)には通常通り消費税が発生する
- ファクタリングの手数料に消費税を加算することはできない
- 国税庁のウェブページでも非課税取引として明記されている
- 悪質なファクタリング会社は消費税を上乗せ請求することがある
- 消費税が加算された見積もりは誤りである可能性が高い
- 債権譲渡登記が必要な契約で司法書士に支払う報酬には消費税が発生する
- 取引の種類によって消費税の扱いが異なるため、区別して処理する必要がある
ファクタリング取引に関連して発生する費用の中には、消費税がかかるものとかからないものがあるため、それぞれを正しく区別して処理をしましょう。不明点がある場合は、税理士や税務署に確認することをお勧めします。
ファクタリングにおける売上の特性
ファクタリング契約を結んでから資金が入金されるまでに決算期末を挟んでしまうケースがあります。この場合、会計上の注意点として、ファクタリング会社からまだ入金されていなくても、売上として計上した金額には課税されるということを理解しておく必要があります。
決算期をまたぐ場合の注意点
- 売上が発生した時点で課税対象となる(現金入金の有無は関係ない)
- ファクタリング会社からまだ入金されていなくても法人税や消費税の納税義務は発生する
- 決算期末が近い時期にファクタリングを検討する場合は、期間を考慮する
- 可能であれば決算期をまたがないタイミングでファクタリングを利用する
- 決算期をまたぐ場合は、税金の支払いに備えた資金計画が必要
- 3社間ファクタリングは契約から入金までの期間が長くなりやすいため、特に注意が必要
- 決算対策としてファクタリングを活用する場合は税理士に相談するのが望ましい
ファクタリングの目的が資金繰りの改善にある以上、税金の支払いによって新たな資金ショートを招くことは避けたいところです。決算期との関係を考慮した計画的にファクタリングを活用しましょう。
まとめ
ファクタリングは売掛金を早期に現金化できる有効な資金調達手段ですが、その会計処理には独自のルールがあります。保証型と買取型の2種類があり、買取型はさらに2社間と3社間に分かれます。それぞれの特性や会計処理の違いを理解することが、正確な仕訳の基本です。
保証型ファクタリングでは保証料を「支払手数料」として処理し、万一の貸倒れ時には「貸倒損失」と「雑収入」の仕訳をします。一方、買取型ファクタリングでは売掛金を「未収入金」に振り替え、手数料を「売上債権売却損」として計上します。
仕訳で悩んだ場合は、税理士や税務署などの専門機関に相談すると解決の糸口が見つかるでしょう。また、ファクタリングは非課税取引であること、決算期をまたぐと未入金でも課税対象になることなど、いくつかの注意点も把握しておく必要があります。
適切な会計処理によって、資金繰りの改善と健全な経営の両立をしましょう。