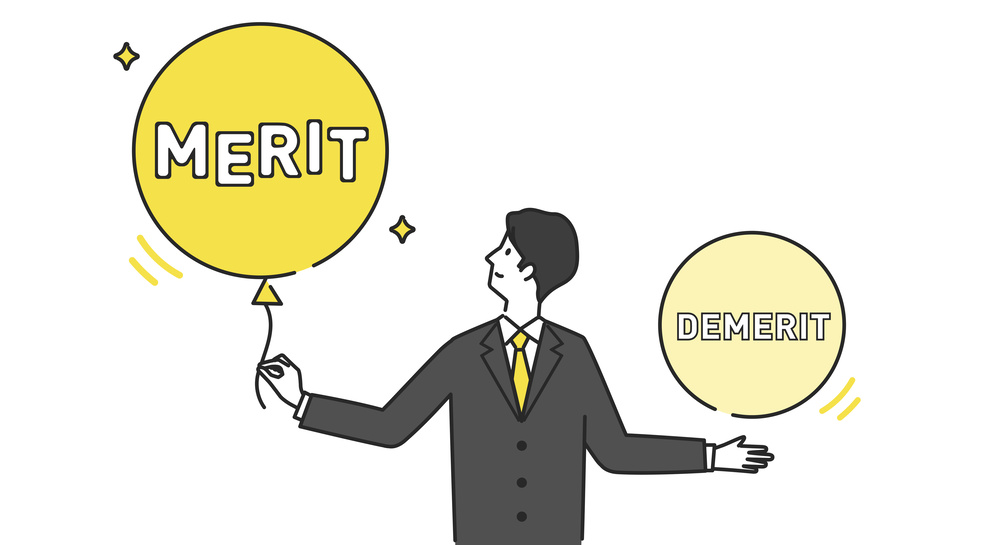家庭から出る生ごみの処理に悩んでいませんか?
毎日のごみ出しの手間や気になる臭い…、これらの悩み、もしかしたら生ごみ処理機を導入することで解消するかもしれません。
近年は環境への配慮から、自治体による購入補助制度も広がっており、導入のハードルは下がってきています。
本記事では、生ごみ処理機の種類や選び方、メリット・デメリットについて解説いたします。これから生ごみ処理機の購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
生ごみ処理機の種類とは?

生ごみ処理機は大きく分けて
- バイオ式
- 乾燥式
- ハイブリッド式
の3種類があります。
それぞれ特徴が異なるため、設置場所や使用頻度、予算などを考慮し、ライフスタイルに合わせて選ぶと良いでしょう。
バイオの力で分解する環境派タイプ
バイオ式は、微生物の働きを利用して生ごみを水と炭酸ガスに分解する方式です。
専用のバイオ基材(チップ)と生ごみを混ぜ合わせることで、効率的に分解を促進します。電気代がほとんどかからず、処理後の残渣を堆肥として活用できる点が特徴ですが、一方で処理には24時間程度と時間がかかり、数か月に一度バイオ基材の交換が必要です。
また、独特の発酵臭があるため、多くの機種が屋外設置向けとなっています。
熱と風で処理する手軽な乾燥式
乾燥式は、熱風で生ごみの水分を蒸発させて処理する方式です。
処理時間は2〜6時間程度と短く、コンパクトな機種が多いため室内での使用に適しています。生ごみを入れてスイッチを押すだけの簡単操作で、誰でも手軽に使えますし、消臭機能も充実しており、キッチンに置いても臭いが気になりにくいのが特徴ですが、ヒーターを使用するため電気代は月に1,000円程度かかります。
使用後は容器の水洗いが必要ですが、全体的に手入れは比較的簡単です。
いいとこ取りのハイブリッド方式
ハイブリッド方式は、乾燥式とバイオ式の長所を組み合わせた処理方式です。
まず熱風で生ごみを乾燥させ、その後微生物の力で分解することで、効率的な処理を実現しています。処理時間は乾燥式より長めですが、バイオ式より短く、電気代も乾燥式より抑えられますし、処理後の残渣はすぐに堆肥として使用可能です。
消臭性能も高く、稼働音も静かなため室内での使用にも適していますが、機種が限られており、価格は他の方式と比べて高めになっています。
暮らしが変わる!導入後のメリット

生ごみ処理機を導入すると、
- 毎日のごみ出しから解放される
- キッチンの衛生環境が改善される
- ごみの減量化を通じて環境保護にも貢献できる
こんなメリットがあります。
処理後の残渣は堆肥として再利用することもできるので、長期的に見ると家事の負担軽減はもちろん、地球環境保全にも貢献できます。
毎日のごみ出しから解放される快適さ
処理機で乾燥・分解された生ごみは、体積が元の5分の1から10分の1程度まで減少するので、ごみ袋の消費も抑えられ、ごみ出しの頻度も大幅に減らすことができます。
同時に、水分が少なくなるため、ごみ出し時の汁漏れの心配もなくなり、カラスや猫による被害の心配も軽減されます。
生ごみの臭いとおさらば!清潔なキッチン
通常、生ごみを放置すると雑菌が繁殖して臭いの原因となりますが、処理機で乾燥や分解をすることで雑菌の繁殖を防ぎます。これにより、生ごみの臭いが部屋中に漂うことがなくなり、キッチン周りを清潔に保つことができます。
生ごみに寄ってくるコバエなどの虫も発生しにくくなり、衛生面での悩みも解消されます。
エコ活動で実感できる環境貢献
生ごみ処理機を使い、家庭から出る生ごみの水分を減らしてからごみ出しをした場合、回収後の焼却処理時に掛かる負担を軽減することができますし、残渣を堆肥として活用すれば環境保全にも役立ちます。
最近は、多くの自治体が生ごみ処理機の購入に対して補助金を設けています。補助金額は自治体によって異なりますが、購入費用の半額程度が補助されるケースも多く、初期費用の負担を抑えることができます。
生ごみ処理機導入前に確認したいデメリット

生ごみ処理機には、導入前に考慮すべきデメリットもあります。
主な課題は、本体価格や維持費用の負担、設置スペースの確保、そして定期的なメンテナンスの必要性です。
処理機本体と維持管理にかかる費用負担
本体価格は2万円台から10万円以上までと幅広く、性能や機能に応じて価格が変わります。そこに維持費用として、電気代やフィルター交換費用などのランニングコストが発生してきます。
乾燥式の場合、電気代は月に1,000円程度。バイオ式では電気代は抑えられますが、数か月に一度のバイオ基材の補充が必要です。
消臭フィルターは半年に1回程度の交換が推奨されており、こちらも定期的な費用負担となります。
設置スペースの確保と音への配慮事項
生ごみ処理機の設置には、ある程度のスペースが必要となります。
特にバイオ式は大型の機種が多く、屋外に設置スペースを確保する必要がありますし、乾燥式は比較的コンパクトですが、それでもキッチンカウンターの一角を占有することになります。
稼働時の音にも注意が必要で、多くの機種は40〜50dB程度の運転音を発するので、深夜の使用時には近隣への配慮が必要となる場合もあります。
毎日の清掃と定期的な部品交換の必要性
生ごみ処理機の使用後は、処理容器の水洗いが必要となります。特に油分の多い生ごみを処理した後は念入りに清掃した方が良いとされています。
消臭フィルターは定期的な交換が必要で、交換時期を過ぎると脱臭効果が低下しますし、バイオ式の場合は、バイオ基材の状態確認や補充、入れ替えなども必要です。
処理機のある生活の始め方ガイド

ウチにも生ごみ処理機が欲しい!と思ったのであれば、まずは設置場所を決め、そのスペースに置けるサイズの機種を選びましょう。処理能力については、家族の人数や生活スタイルに合わせて決めると良いです。
メーカーによって推奨される使用方法が異なるため、基本的な初期設定や使用方法を確認するのはもちろん、取扱説明書に書かれている注意事項にも目を通すようにしましょう。
また、自治体の補助金制度を利用する場合の、申請のタイミングや対象機種の確認も忘れずに行うと良いでしょう。
設置場所から考える機種選び
生ごみ処理機をキッチン内に設置する場合は、コンパクトで消臭機能の高い乾燥式がおすすめです。換気のしやすさやコンセントの位置、周囲のスペースにも注意を払う必要があります。一方、屋外に設置する場合は、雨風を避けられる場所を選ぶことと、電源の確保が必要になります。バイオ式は屋外設置が基本となるので、発酵臭への対策もしっかり考えておきましょう。
家族構成で決める処理能力の目安
一般的に、1人当たりの1日の生ごみ排出量は約300〜500gと言われています。例えば、4人家族の場合は1日に1.2〜2kg程度の処理能力が必要となります。ただし、毎日料理をする家庭や、外食が多い家庭では排出量が大きく異なるため、実際の生活パターンも考慮に入れましょう。
処理時間は、乾燥式は2〜6時間程度、バイオ式は24時間程度かかるため、生活リズムに合った処理時間の機種を選ぶことが大切です。
使い始めの基本をマスター
生ごみ処理機を使い始める際は、まず取扱説明書をしっかり確認しましょう。投入できる生ごみの種類や量、水切りの程度など、基本的なルールを押さえることが重要です。
野菜くずや果物の皮など水分の多いものは、しっかり水を切ってから投入し、魚の骨や貝殻など硬いものは細かく砕いてから入れると効率的に処理できます。
ライフスタイル別!最適な選び方

生ごみ処理機の選び方は、ライフスタイルによって大きく異なります。
ここでは
- 共働き家庭の場合
- マンション暮らしでの場合
- 料理好きな人の場合
の3パターンで説明します。
共働き家庭の時短活用術
出勤前に生ごみを投入して、帰宅後に処理済みのごみを取り出す。こんなサイクルにすると、朝夕の忙しい時間帯を効率的に過ごすことができます。
こういう家庭の場合は、タイマー機能付きの機種を選ぶと良いでしょう。
また、休日にまとめて処理する場合は、生ごみを一時保管できる密閉容器を用意しておくと便利です。
マンション暮らしでの快適使用
マンション暮らしには、コンパクトで静音性の高い機種が向いています。
キッチンカウンターに設置する場合は、作業スペースをしっかり確保しておくことを忘れずに。運転中は音の心配もあるため、近隣への配慮として深夜の使用は可能な限り避け、朝や日中の時間帯に処理を行うことをおすすめします。
ベランダに設置する場合は、雨風を避けられる場所を選び、必要に応じて簡易の屋根やカバーを設置すると良いでしょう。
料理好きさんの活用テクニック
料理をする頻度の高い家庭では、野菜の皮むきや魚のアラなど、調理過程で出る生ごみをその都度投入できる、処理能力の高い機種を選ぶと良いでしょう。
バイオ式やハイブリッド式なら、処理後の残渣を家庭菜園の堆肥として活用できますし、生ごみの種類や量に応じて処理モードを使い分けることで、より効果的な処理が可能になります。
まとめ
生ごみ処理機は、日々の生活を快適にする便利な家電です。メリットとして、ごみ出しの手間軽減や臭い対策、環境への貢献が挙げられます。一方で、初期費用や維持費用、メンテナンスの手間などのデメリットもあります。
導入を検討する際は、ライフスタイルに合った処理方式や機能であるかを調べ、そして設置場所やメンテナンス面も考慮しておく必要があります。自治体による補助金制度も活用できるため、これについても導入前に確認することをおすすめします。
なお、フィルター交換や清掃などの基本的なお手入れを習慣づけることで、生ごみ処理機を長く快適に使い続けることができます。
現在は様々なタイプの生ごみ処理機が販売されていますので、導入を検討している方は、本記事を参考に自分に合った機種を選んでみてください。