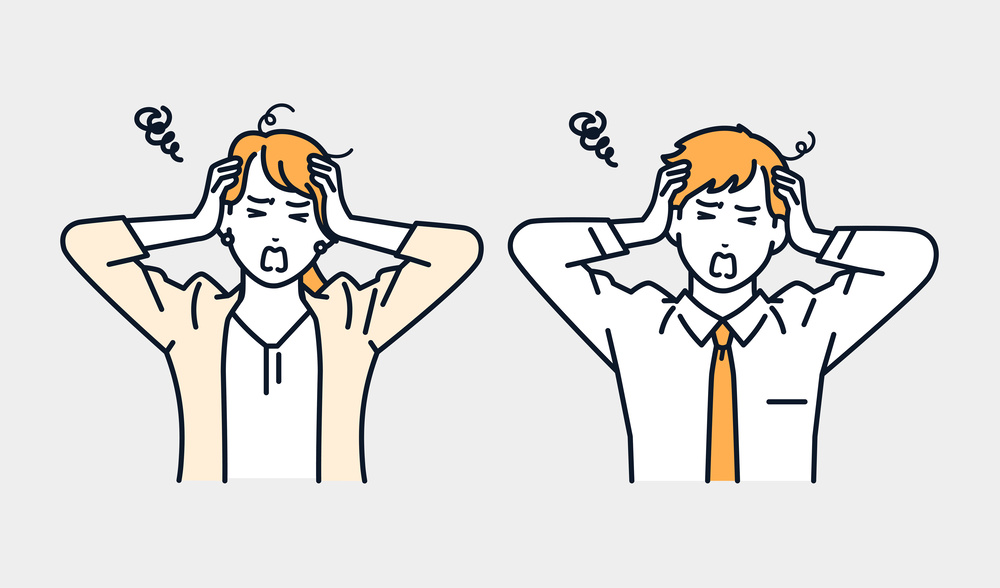生ごみ処理機は、家庭から出る生ごみを効率的に処理し、臭いや虫の発生を抑える便利な家電として注目されています。しかし、高額な初期費用やランニングコスト、メンテナンスの手間など、購入後に後悔するケースも少なくありません。
本記事では、生ごみ処理機のメリット・デメリットの説明から、製品選びのポイントまで紹介します。
生ごみ処理機を購入して後悔する理由とは

生ごみ処理機を購入したものの、「要らなかったかも……」と後悔する理由として、下記のものが挙げられます。
- 初期投資が高い
- 電気代などのランニングコストの問題
- 処理能力が期待と異なる
- メンテナンスに手間がかかる
- 臭いや清掃の問題
これらについて確認していきましょう。
初期投資が高い
生ごみ処理機の価格帯は、方式や機能によって2万円から10万円以上までと幅広く設定されています。とくにハイブリッド式や高機能な製品は、8万円以上の投資が必要となります。
設置工事が必要な機種の場合は、工事費用も別途必要です。自治体による購入補助金制度を利用できる場合もありますが、それでも一般的な家電製品と比較すると大きな初期投資となります。
導入を検討する際は、まず予算設定をしっかりと行い、補助金制度の有無も確認することをおすすめします。
電気代などのランニングコストの問題
生ごみ処理機の運用には、毎月の電気代に加えて、定期的な消耗品の交換費用が発生します。電気代は機種により異なりますが、乾燥式の場合、1回あたり30~50円程度、月額では1,000円前後かかることも。
脱臭フィルターは3~6ヶ月ごとの交換が推奨され、1個あたり3,000~5,000円程度の費用がかかりますし、バイオ式やハイブリッド式では微生物の活性を保つための基材の補充も必要となるので、これらの維持費用も事前に把握しておくと良いでしょう。
処理能力が期待と異なる
一般的な家庭用生ごみ処理機の処理能力は、1回あたり700gから2kg程度です。4人家族の1日の生ごみ量が約1kg程度とされているので一見十分な容量に思えますが、実際は不十分と感じることがあるようです。
処理時間も機種により2時間から10時間程度かかり、思ったより時間がかかると感じる方も少なくありません。
家庭から出る生ごみの量をある程度把握しておき、機種選びの際の基準にすると良いでしょう。
メンテナンスに手間がかかる
日々のメンテナンスには、定期的な内部の清掃や、フィルター交換などが必要となります。
乾燥式の場合、処理後の生ごみの取り出しや処理容器の洗浄が毎回必要で、脱臭フィルターの定期交換や、内部の清掃も必要不可欠です。バイオ式では基材の補充や攪拌といった作業も加わります。
また、故障時の修理や部品交換なども必要になる場合があります。
これらの手間を軽減したい場合は、自動清掃機能付きの機種を選べばいいでしょう。
臭いや清掃の問題
生ごみ処理機の使用時には、処理方式によって異なる臭いの問題が発生します。
乾燥式では処理時の焦げ臭さが、バイオ式では発酵時の独特な臭いが気になることがありますし、内部の清掃が不十分だと、カビや雑菌が発生してさらに不快な臭いの原因となる可能性があります。
ただし、生ごみ処理機の置き場所を工夫することや、適切な換気を行うこと、また日々の清掃を怠らないようにすることで、これらの問題は回避できます。
生ごみ処理機を購入するメリット
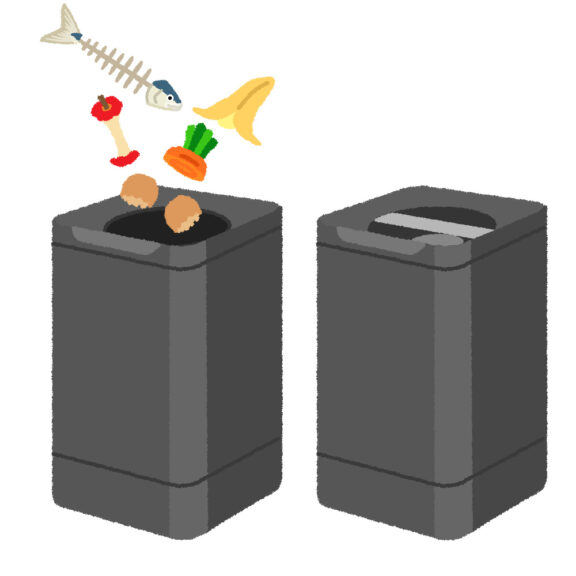
生ごみ処理機は、使うことで臭いや虫の発生を抑制し、衛生的なキッチン環境を維持できるだけでなく、ごみの減量化による環境への貢献も期待できます。
ここでは、4つのメリットについて説明します。
- 生ごみの臭いを軽減できる
- 生ごみの量を軽減できる
- 生ごみをすぐに処理できる
- 生ごみを肥料にできる
生ごみの臭いを軽減できる
生ごみ処理機を使用することで、生ごみ特有の不快な臭いを大幅に軽減できます。
処理方式によって仕組みは異なりますが、乾燥式では高温の熱風で水分を飛ばすことで腐敗を防ぎ、バイオ式では微生物の働きで効率的に分解することで臭いの発生を抑制します。
とくに夏場は、生ごみの腐敗が進みやすく臭いが発生しやすい時期ですが、処理機を使用することでこの問題をかなり軽減することができます。
生ごみの量を軽減できる
生ごみ処理機を使用することで、生ごみの量を元の体積の10分の1程度まで減らすことが可能です。その結果、ごみ出しの頻度を大幅に減らすことができ、ごみ袋の使用量削減にもつながります。
ごみの減量は収集や焼却に係るエネルギーの削減にもつながり、環境負荷の低減にも貢献します。
生ごみをすぐに処理できる
生ごみ処理機があれば、料理中に発生した生ごみをその場ですぐに処理できます。
三角コーナーに溜めておく必要がなく、ごみ収集日まで溜め込んでおく必要もないため、虫の発生や臭いの問題も防げ、シンク周りを常に清潔に保つことができます。
生ごみを肥料にできる
処理後の生ごみは、バイオ式やハイブリッド式の場合、そのまま良質な有機肥料として活用できます。微生物による分解過程で生成される堆肥は、土壌改良材としても優れた効果を発揮します。乾燥式で処理した場合でも、適切な後処理を行うことで堆肥化が可能です。
家庭菜園やガーデニングを楽しむ方にとっては、生ごみを資源として循環させることができる点で大きなメリットとなります。
生ごみ処理機に入れてはいけないもの

生ごみ処理機は全ての生ごみを処理できるわけではありません。処理できない食材を誤って投入すると、故障や性能低下の原因となる可能性があります。下記のものは投入しないように注意してください。
- 硬いもの
- 化学物質
- プラスチックや金属
- 油分と水分が多いもの
必ず、取扱説明書に記載されている「処理できない食材」を確認しておきましょう。
硬いもの
機種によって処理可能な硬さの基準は異なりますが、果物の種子(桃や梅の種など)、貝殻、カニなどの甲殻類の殻、魚や鶏の骨などの硬いものは、処理機の刃を損傷させたり、故障の原因となる可能性があります。
とうもろこしの芯なども繊維質が強く処理が困難で、機器に負担をかける可能性があります。
化学物質
洗剤や漂白剤、化粧品などの化学物質は、処理機内の微生物を死滅させたり、機器の部品を劣化させる可能性があるため、投入は絶対に避けてください。タバコの吸い殻や灰なども同様に処理できません。
バイオ式やハイブリッド式の場合、化学物質により微生物の活性が低下すると処理能力が著しく低下する可能性があり、機器の故障や処理効率の低下をまねく原因にもなりますので、これらは通常のごみとして処分しましょう。
プラスチックや金属
ラップやビニール袋、アルミホイル、割り箸などは生分解性がなく、処理機内で分解されません。とくに金属類は機器を損傷させる可能性が高いため、投入前に生ごみと一緒に混入していないかよく確認しましょう。
また、プラスチック製品は、熱で溶けて内部に付着すると清掃が困難になったり、故障の原因となる可能性があります。
油分と水分が多いもの
揚げ物の油やスープなどの液体、水分の多い野菜くずは、処理機内部をベタつかせ、悪臭の原因となります。とくに油分は処理機内部に付着してしまうと除去が困難になり、性能低下の原因となります。
水分の多い生ごみは、事前にしっかりと水切りをしてから入れるようにしましょう。
その他に注意したいもの
- 柑橘類の皮は、一度に大量投入すると処理効率が低下する可能性があるため、少量ずつ投入しましょう。
- 腐敗した食べ物やペットの糞は絶対に投入してはいけません。これらは悪臭の原因となるだけでなく、処理機の性能低下を招く可能性があります。
- 発火性のある物質や高温の食材も投入してはいけません。
なお、機種によって投入できない物は異なるため、取扱説明書をよく確認しましょう。
生ごみ処理機の選び方とポイント

家族構成や生活スタイルに合わせて、下記の要素を総合的に検討し、希望に合った機種を選択するとよいでしょう。
- 機能性を重視する
- 設置場所に対して適切なサイズを選ぶ
- 予算と性能のバランスを考える
これらのポイントについて解説します。
機能性を重視する
生ごみ処理機の機能性を評価する際は、処理方式、処理容量、運転音、脱臭性能などを総合的に検討しましょう。
処理方式は大きく分けて乾燥式、バイオ式、ハイブリッド式があり、それぞれに特徴があります。
| メリット | デメリット | |
| 乾燥式 | 比較的安価で手軽に使える | 処理後、ごみの取出しが必要 |
| バイオ式 | 環境に優しく静音性が高い | 微生物の管理が必要 |
| ハイブリッド式 | 乾燥式とバイオ式の両方の利点を併せ持っている | 価格が高め |
自動運転機能や予約機能など、便利な付加機能の有無も確認するとよいでしょう。
設置場所に対して適切なサイズを選ぶ
生ごみ処理機の設置には、製品本体のサイズに加えて、使用時やメンテナンス時の作業スペースも考慮する必要があります。一般的な製品サイズは、幅30cm以上、奥行30cm以上、高さ50cm以上となっており、これに加えて周囲に10cm程度の余裕スペースを設けると良いでしょう。
設置場所を検討する際は、以下のポイントに注意が必要です。
- キッチンの空きスペース
- 電源コンセントの位置
- 換気が可能か
- メンテナンス時のアクセスのしやすさ
- 周辺家電への干渉
とくに屋外に設置する場合は、雨風を避けられる場所を選び、防水対策された電源の確保も大切となります。
予算と性能のバランスを考える
生ごみ処理機の選択では、初期費用に加えて、電気代やメンテナンス費用などのランニングコストが掛かることを考慮しておく必要があります。
価格帯は2万円から10万円以上まで幅広く、高価格帯の製品ほど処理能力や静音性、脱臭性能が優れている傾向にあります。電気代は月額500円から2,000円程度、フィルター交換などの消耗品費用も定期的に発生します。
自治体の補助金制度を利用できる場合は、購入費用を抑えることが可能です。
まとめ
生ごみ処理機は、適切に選択・使用することで快適な生活環境を実現できる便利な家電です。購入前には、初期費用やランニングコスト、メンテナンスの手間などのデメリットを十分に理解し、自身の生活スタイルに合った機種を選択することが重要です。また処理できない物の確認や、定期的なメンテナンスを行うことで、より効果的に活用することができます。
環境への配慮や生活の質の向上を目指す方にとって、購入を検討する価値のある製品といえるでしょう。