ファクタリングを検討する中で、「取引や手数料に消費税はかかるのだろうか?」という疑問を持たれている方も多いのではないでしょうか。
資金繰りの改善に役立つファクタリングですが、余計な出費を増やしたくないという心配は当然です。効率的な資金調達を行うためには、正確な費用把握が欠かせません。
本記事では、ファクタリング取引が非課税となる理由や、例外的に消費税がかかるケース、悪徳業者の見分け方までを詳しく解説します。この知識を身につければ、無駄な出費を避け、適切なファクタリング会社を選んで効果的な資金調達が可能になるでしょう。
ファクタリング取引とは

ファクタリングとは、企業や個人事業主が保有する売掛金を売却することでスピーディーに資金調達ができる金融サービスです。売掛先から入金があるまで待つことなく、売掛金を現金化できるため、資材・機材代の支払いや人件費確保など、急な資金需要に対応できるメリットがあります。
契約方法には「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」の2種類があります。2者間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社のみで契約を行うため、最短即日での入金が可能ですが、手数料が高めに設定されています(相場は10%〜20%程度)。一方、3者間ファクタリングは、売掛先も契約に参加するため手続きに時間がかかるものの、手数料が比較的低く(相場は1%〜9%程度)、貸し倒れリスクも軽減できます。
不動産担保融資などが利用できない中小企業や個人事業主にも活用しやすい資金調達手段として、近年注目を集めています。ファクタリングは売掛債権の売買取引であり、借入ではないため、赤字企業でも審査に通りやすいという特徴もあります。
消費税とはどのような税金か
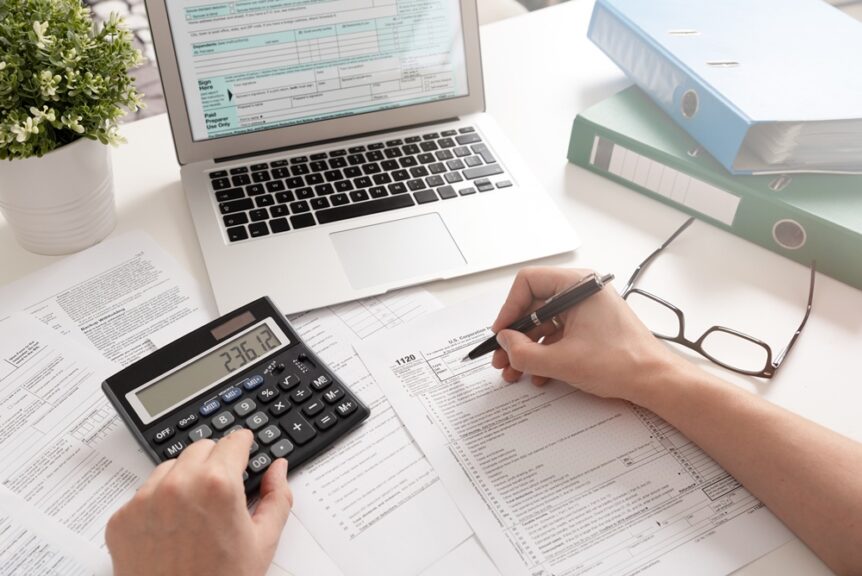
ファクタリング取引と手数料に消費税がかかるのかを理解するためには、まず消費税の基本的な仕組みを押さえておく必要があります。消費税は商品やサービスの購入時に発生する間接税で、一般的な取引では10%が課税されますが、すべての取引に消費税がかかるわけではありません。
ファクタリングの場合、どのような条件で消費税が課税され、あるいは非課税となるのか、その基準を明確にしておきましょう。
消費税の非課税取引について
消費税は商品やサービスの消費に対して広く公平に課税される税金です。しかし、すべての取引に課税されるわけではなく、一部は非課税取引として定められています。消費税が課税されない取引には、「不課税取引」「非課税取引」「免税取引」の3種類があります。
非課税取引は、消費税の課税対象に該当する取引であっても、性質上の理由や社会政策的配慮から課税しないものとして定められています。具体的には、土地の譲渡・貸付け、有価証券等の譲渡(国債、株券、金銭債権など)、預貯金の利子、貸付金の利子、社会保険医療などが該当します。ファクタリングによる売掛債権の譲渡は「有価証券等の譲渡」に分類され、これにより非課税取引となります。
国税庁の定めによると、「消費税は財貨やサービスの流れを通して消費に負担を求める税」であるため、ファクタリングのような金融取引は消費税の課税になじまないと解釈されています。
消費税の課税対象取引とは
消費税の課税対象となる取引は、国税庁によって明確に定められています。具体的には「国内における取引」「事業者が事業として行う取引」「対価を得て行う取引」「資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供である取引」の4つの条件をすべて満たす取引が課税対象となります。
国内取引であることは、日本国内で行われる取引だけが対象となります。国外との取引や海外での消費は基本的に課税されません。事業者が事業として行う取引については、法人はすべての取引が事業として認められますが、個人事業主は事業者の立場と消費者の立場を兼ねているため、個人的な取引(自家用車の売却など)は課税対象外となります。
また、対価を得て行う取引とは、資産の譲渡等に対して反対給付として対価を受け取る取引を指します。寄附金や補助金、宝くじの当選金などは対価性がないため課税対象外です。最後に、資産の譲渡・貸付・役務の提供にあたる取引であることが必要ですが、ファクタリングは「金銭債権の譲渡」に該当するため、原則として消費税の課税対象外となります。
ファクタリング手数料の内訳と消費税の関係性

ファクタリングにかかる費用と一口にいっても、その内訳は多岐にわたり、消費税の課税対象となるかどうかも項目ごとに異なります。取引の透明性を保ち、想定外の税負担を避けるためには、それぞれの費用における消費税の扱いを正確に把握しておくことが大切です。ファクタリング取引と関連する費用において、どの部分が非課税で、どの部分に消費税がかかるのか、見ていきましょう。
- ファクタリング手数料は消費税非課税対象
- 掛け目には消費税がかからない?
- 事務手数料は消費税がかかる?
- 登記費用の変動と費用について
- 印紙税は消費税の対象外?
- 出張時の消費税課税について
以下では、主要な費用項目ごとに消費税の取り扱いについて解説します。
ファクタリング手数料は消費税非課税対象
ファクタリングの主要な費用である手数料には、消費税はかかりません。これは、有価証券の譲渡は非課税取引と定められており、ファクタリングは金銭債権の譲渡に該当するため非課税取引とみなされているからです。
ファクタリング会社の売上の大半はこの手数料です。利用者から提出された書類を審査した上で手数料率が決定され、審査後に利用者の口座に資金が振り込まれます。ただし、この時点でファクタリング会社は手数料をまだ回収できていません。支払期日を迎えて売掛先から売掛金が入金される、または利用者が回収した売掛金をファクタリング会社に送金することで、初めて手数料を回収する仕組みです。
この手数料が非課税となる根拠は、国税庁が定める「預金や貸付金の利子など」に該当するためです。金銭債権の譲渡に伴って生じる手数料は、名目にかかわらず金銭債権の譲受対価として非課税となります。なお、手数料に消費税を上乗せして請求してくる業者は悪徳業者の可能性が高いため、見積りの際に詳細をよく確認することが大切です。
掛け目には消費税がかからない?
ファクタリングの掛け目も消費税の課税対象外です。掛け目とは、売掛金の金額に対する買取率をあらかじめ決めた上で売掛金を買い取る方法で、一部のファクタリング会社で採用されています。
例えば、掛け目が95%の場合、買い取る売掛金が100万円であれば、そのうち5万円が掛け目となり、95万円が買取債権額です。この買取債権額95万円に対して手数料率が10%なら、手数料は9万5,000円となります。掛け目の5万円については、売掛金の回収後に返還されるため、ファクタリング会社の利益にはならず、非課税売上にも該当しません。
掛け目は売掛金を現金化する際の買取率を示すものであり、本質的には金銭債権の譲渡に関わる取引の一部です。そのため、掛け目部分についても消費税は課税されません。
もし掛け目部分に対する消費税を上乗せして請求されている場合は、悪徳業者である可能性があるため注意が必要です。掛け目が設定されるファクタリング会社を利用する際は、消費税の有無についても必ず確認しましょう。
事務手数料は消費税がかかる?
事務手数料とは、ファクタリングの手続きや事務作業に対して発生する手数料です。この事務手数料は、基本的に消費税の課税対象となります。その理由は、事務作業は役務の提供に該当し、その対価として支払われるからです。
国内で事業を営むファクタリング会社と契約してファクタリングを利用する場合、事務手数料に対する消費税の負担義務が発生します。ファクタリングの事務手数料について、国税庁は明確な見解を示していませんが、金銭消費貸借契約にかかる事務手数料については役務の提供の対価であり、消費税法で定められている金銭の貸付に対する利子には該当しないため、課税対象としています。
この考え方からすると、ファクタリングの事務手数料も同様に課税対象と考えるのが妥当です。ファクタリング会社が審査や契約締結など、事務手続き全般にかかる費用を「事務手数料」として請求する場合、その金額に対して10%の消費税が課税されることを念頭に置いておきましょう。なお、「事務手数料無料」とするファクタリング会社も多く存在します。
登記費用の変動と費用について
ファクタリング会社によっては、契約時に債権譲渡登記が必要となる場合があります。とくに2者間ファクタリングを利用する場合、債権譲渡登記を求められることが多いでしょう。この債権譲渡登記には消費税が一部発生するため、注意が必要です。
債権譲渡登記を行う際の費用には複数の項目があり、それぞれで消費税の課税・非課税が異なります。まず、登記に必要な登録免許税は非課税。登録免許税自体が税金であり、これに消費税を上乗せすると二重課税になるためです。一方、債権譲渡登記の代理手続きを司法書士に依頼する際の報酬は消費税の課税対象となります。 この報酬は司法書士が提供する役務に対して支払うものであり、国税庁が定める消費税の課税対象である「役務の提供」に該当します。ファクタリングの利用時には、通常、ファクタリング会社が司法書士へ債権譲渡登記の手続きを依頼し、登記にかかった費用をまとめて利用者へ請求することが多いでしょう。その際、内訳をよく確認して、どの部分に消費税がかかっているのかを把握することが重要です。
印紙税は消費税の対象外?
ファクタリングの契約において必要となる印紙税は、消費税の課税対象外です。ファクタリング契約に限らず、税金に対して消費税が課税されることはありません。
取引金額が1万円未満の場合は印紙税がかかりませんが、1万円以上の契約には印紙税が発生します。ファクタリングの取引はある程度まとまった金額になることが多いため、ほとんどの場合で印紙税が発生するでしょう。印紙税の計算基準となる金額は、譲渡する債権の金額です。
印紙税が課税対象外となっている理由は、ファクタリング会社の売上にはならないからです。印紙税は国に納付される税金であり、ファクタリング会社は単にその納付を代行しているに過ぎません。したがって、ファクタリング会社が印紙税に消費税を上乗せして請求することはできません。
契約時には内訳をしっかり確認し、印紙税に消費税が加えられていないかをチェックしましょう。なお、電子契約を利用した場合は印紙税自体が不要となるケースもあります。
出張時の消費税課税について
ファクタリングの契約時には、対面での詳細確認を行うケースも少なくありません。ファクタリング会社と利用者の距離が離れている場合、ファクタリング会社の担当者が出張して利用者のもとを訪ねることもあります。その際に発生する出張費用については、内容によって消費税の取り扱いが異なります。
出張費用は主に、移動にかかった実費(交通費)と出張手数料に分けられます。電車代、飛行機代、タクシー代などの交通費は、すでに消費税が含まれている内税のため、非課税扱いとなります。これらの実費に消費税を上乗せすると二重課税となるため、交通費については消費税が課税されません。
一方、出張手数料は消費税の課税対象となります。出張手数料は、出張対応という役務に対して支払う対価であるため、国税庁が定める消費税の課税対象である「役務の提供」に該当します。
このように、ファクタリング会社の出張に関わる費用は、内容によって課税・非課税の考え方が異なります。出張費用を請求された場合は、内訳について細かく確認し、適切に消費税が課税されているかを確認することが大切です。
ファクタリング会社から請求される消費税に注意

ファクタリングの手数料は基本的に非課税取引となりますが、中には消費税を上乗せして請求してくる業者も存在します。こうした請求を受けた場合は、その業者が悪徳業者である可能性を疑うべきです。
国税庁の定めによると、ファクタリングの手数料は「有価証券等の譲渡」に該当し、非課税取引として明確に位置付けられています。ファクタリングの基本取引や手数料に消費税を加算することはできないため、万が一消費税を上乗せした見積りを提示されたら、取引を中断し、別の信頼できるファクタリング会社への相談をおすすめします。
ただし、ファクタリングに関連する費用の一部、特に司法書士への報酬や事務手数料、出張手数料などは「役務の提供」に該当するため消費税の課税対象となります。 請求書の内訳を細かく確認して、どの項目に消費税がかかっているのかを把握することが重要です。消費税が適正に課税されているかどうかは、業者の信頼性を見極める重要な指標となります。
まとめ
ファクタリングの手数料に消費税がかかるかどうかは、資金調達を効率的に行う上で把握しておくべき重要なポイントです。本記事でご説明したように、ファクタリング取引と手数料は国税庁により「有価証券等の譲渡」に分類され、非課税取引となります。
ただし、事務手数料や司法書士報酬、出張手数料など一部の費用には消費税が課税されることを理解しておきましょう。消費税を請求されたときには、どの項目に課税されているのか内訳を確認することが大切です。とくに基本的な手数料に消費税を上乗せして請求する業者は悪徳の可能性が高いため注意が必要です。
この知識を活用して適切なファクタリング会社を選び、無駄な出費を抑えつつ効果的な資金調達を実現しましょう。









