ファクタリングは、売掛債権を早期に現金化できる資金調達手段として広く知られています。しかし、近年、このファクタリングが「与信管理」にも役立つという側面が注目されています。与信管理は、企業が安全に取引を行う上で不可欠なリスク管理手法です。一見すると資金調達とリスク管理は別の目的のように思えますが、ファクタリングの仕組みを理解すると、その関連性が見えてきます。本記事では、与信管理の基本から、なぜファクタリングが与信管理に活用できるのか、その具体的なメリットや注意点について、詳しく解説していきます。
与信管理とは?

与信管理とは、企業が取引先に対して信用を供与する(=与信)際に、その取引先の支払い能力を評価し、安全に取引を行えるように管理する活動全般を指します。具体的には、取引を開始する前に相手企業の信用情報を調査・分析し、どの程度の金額までなら掛け売り(信用取引)をしても問題ないかという「与信限度額」を設定します。そして、取引開始後も定期的に取引先の経営状況などを把握し、必要に応じて与信限度額を見直すなど、継続的な管理を行います。この与信管理を適切に行うことで、売掛金の未回収リスク(貸倒れリスク)を最小限に抑え、安定した経営基主盤を維持することが可能になります。
与信限度額は売掛先の信用度によって見直しが必要
一度設定した与信限度額は、永続的なものではありません。取引先の経営状況や財務内容は、市場環境の変化や経営努力によって常に変動する可能性があるからです。そのため、最初に設定した与信限度額が、将来にわたって適切であり続けるとは限りません。したがって、企業は定期的に、あるいは取引先の経営状態に変化が見られた際に、その信用度を再評価し、与信限度額を見直す必要があります。例えば、業績が向上している企業に対しては限度額を引き上げ、逆に業績が悪化している、あるいは支払い遅延が発生しているような企業に対しては限度額を引き下げる、といった判断が求められます。このような継続的な見直しこそが、実効性のある与信管理の要となります。
適切な与信限度額の設定が求められる理由は?
適切な与信限度額を設定することは、企業経営において極めて重要です。その主な理由は、売掛金の未回収、すなわち貸倒れリスクを効果的に管理するためです。もし、支払い能力を超えた過大な与信を取引先に与えてしまうと、万が一その取引先が倒産した場合、多額の損失を被り、自社の経営までをも揺るがしかねません。一方で、リスクを恐れるあまり与信限度額を低く設定しすぎると、販売機会を逃し、売上の拡大を妨げてしまう可能性もあります。つまり、適切な与信限度額の設定とは、取引先の信用力を見極めた上で、リスクとリターンのバランスを取りながら、安全かつ最大限の取引を実現するための重要な経営判断なのです。
ファクタリングが与信管理として活用できる理由は?

ファクタリングが与信管理に役立つとされる背景には、その審査プロセスと仕組みに理由があります。ファクタリングは、利用企業が保有する売掛債権をファクタリング会社が買い取るサービスですが、その際、ファクタリング会社は売掛債権の回収可能性を評価します。この評価の中心となるのが、売掛金の支払い元である「売掛先」の信用力です。つまり、ファクタリングを利用する過程で、第三者であるファクタリング会社による売掛先の信用評価が行われるため、これが間接的に与信管理の機能を果たすというわけです。以下で、その具体的な理由をさらに詳しく見ていきましょう。
審査で重要なのは売掛先の信用力
ファクタリングの審査において最も重視されるのは、ファクタリングを利用する企業(納入企業)の信用力ではなく、売掛金の支払いを行う「売掛先」企業の信用力です。なぜなら、ファクタリング会社にとっての最大のリスクは、買い取った売掛債権が売掛先から回収できなくなることだからです。そのため、ファクタリング会社は独自のノウハウやデータベースを用いて、売掛先の財務状況、支払実績、業界での評判などを徹底的に調査・分析します。この第三者による客観的な売掛先の信用評価プロセスが、ファクタリングを利用する企業にとって、自社の与信判断を補強する、あるいは裏付ける情報として活用できるのです。
ファクタリング利用の手数料は信用力で決定する
ファクタリングを利用する際には、ファクタリング会社に対して手数料を支払う必要があります。この手数料率は、様々な要因によって決定されますが、最も大きな影響を与えるのが売掛先の信用力です。売掛先の信用度が高く、売掛金の回収可能性が高いと判断されれば、ファクタリング会社のリスクは低くなるため、手数料率は低く設定される傾向にあります。逆に、売掛先の信用度が低いと判断されれば、未回収リスクが高まるため、手数料率は高く設定されます。この手数料率の高低が、間接的に売掛先の信用度を示す指標となり得ます。定期的に同じ売掛先の債権でファクタリングを利用していれば、手数料率の変動を通じて、その売掛先の信用状態の変化を察知する手がかりにもなり得ます。
売掛先の信用度が高いと契約条件も良くなる
売掛先の信用度が高いと評価された場合、それはファクタリング契約全体の条件にも好影響を与える可能性があります。前述の通り、手数料率が低くなる傾向にあるのはもちろんのこと、売掛債権の買取可能額(掛け目、買取率)が高く設定されたり、審査や入金までのスピードが早くなったりすることも期待できます。ファクタリング会社としても、優良な売掛先の債権は積極的に買い取りたいと考えるため、より有利な条件を提示しやすくなるのです。このように、ファクタリングを利用した結果として提示される契約条件は、単に資金調達の条件というだけでなく、売掛先の信用力を客観的に示すバロメーターとしても機能するわけです。
利用の度に売掛先の情報のアップデートが可能
ファクタリングは、一度きりの利用だけでなく、継続的に利用することも可能です。そして、ファクタリングを利用するたびに、ファクタリング会社は該当する売掛先の信用情報を再評価します。これは、取引先の経営状況が常に変動する可能性があるため、最新の情報に基づいてリスクを判断する必要があるからです。つまり、定期的に特定の売掛先の債権でファクタリングを利用することは、継続的にその売掛先の信用状態に関する最新の評価(審査結果)を得られることを意味します。自社だけで与信管理を行う場合、情報の収集や分析に限界があることもありますが、ファクタリングを活用することで、外部の専門家による定期的な信用チェックの機会を得られるのです。
与信管理として活用するファクタリングのメリット

ファクタリングを与信管理のツールとして捉えた場合、いくつかの具体的なメリットが考えられます。単に売掛先の信用情報を得るだけでなく、資金繰りの改善やリスク回避といった、ファクタリング本来の利点と組み合わせることで、より効果的な経営管理が可能になります。また、利用の柔軟性や、他の金融取引への影響が少ない点なども、企業にとっては大きな魅力となるでしょう。ここでは、ファクタリングを与信管理として活用する際の主なメリットを挙げていきます。
資金調達をしながら与信管理ができる
ファクタリングを与信管理に活用する最大のメリットは、本来の目的である早期の資金調達と、売掛先の信用力評価という与信管理の機能を同時に実現できる点です。通常の与信管理では、信用調査会社を利用するなど別途コストや手間がかかる場合がありますが、ファクタリングであれば、資金繰りを改善するという直接的な効果を得ながら、そのプロセスの中で間接的に売掛先の信用度に関する外部評価を知ることができます。特に、手数料率や買取条件といった形で示される評価は、具体的な取引判断の参考になります。資金ニーズとリスク管理ニーズを同時に満たせる、効率的な手段と言えるでしょう。
未回収リスクの回避
特に「償還請求権なし(ノンリコース)」の契約でファクタリングを利用した場合、売掛先の倒産などによって売掛金が回収不能となった場合でも、ファクタリング利用企業はその責任を負う必要がありません。つまり、売掛金の未回収リスクをファクタリング会社に移転することができるのです。これは、単に売掛先の信用度を測るだけでなく、実際に貸倒れが発生するリスクそのものを回避できるという、極めて強力なリスクマネジメント手法です。与信管理の最終的な目的が貸倒れ損失の防止であるならば、ノンリコース・ファクタリングはその目的を直接的に達成する手段の一つとなり得ます。
単発での利用ができる
ファクタリングサービスの中には、特定の売掛債権のみを対象として、一度きり、あるいは必要な時にだけ利用できるものも多く存在します。継続的な取引契約を結ぶ必要がないため、例えば、新規の取引先で信用力に不安がある場合や、特定の大型案件で未回収リスクをヘッジしたい場合など、スポット的なニーズに対応しやすいのが特徴です。このように、必要なタイミングで、特定の売掛先や売掛債権に絞って利用できる柔軟性は、与信管理のツールとしても使い勝手が良いと言えます。全ての取引で利用する必要はなく、リスクが高いと感じる取引を選択して利用することで、効率的なリスク管理が可能です。
売掛先の承諾不要で利用できる
ファクタリングには、主に「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」の2種類があります。このうち2社間ファクタリングは、ファクタリング利用者とファクタリング会社の2社間のみで契約が完結し、売掛先にファクタリング利用の事実を通知したり、承諾を得たりする必要がありません。そのため、売掛先に知られることなく、その信用力を(間接的に)評価し、かつ資金調達やリスク移転を行うことが可能です。取引先に資金繰りの懸念を知られたくない場合や、取引関係への影響を避けたい場合に有効な方法です。この秘匿性の高さも、与信管理の一環としてファクタリングを活用する際のメリットとなり得ます。
自社の与信への影響がない
ファクタリングは、銀行融資などの借入とは異なり、売掛債権という資産の売却(譲渡)という側面が強い取引です。そのため、一般的に企業の負債として計上されることはなく、バランスシートを悪化させません。また、信用情報機関に利用履歴が登録されることも通常はありません。したがって、ファクタリングを利用したことが、自社の信用評価に悪影響を与えたり、将来的な銀行融資の審査で不利になったりする可能性は低いと考えられます。財務体質への影響を抑えながら、資金調達と与信管理(リスクヘッジ)を行える点は、特に借入枠に余裕がない企業や、財務指標を重視する企業にとって大きなメリットと言えるでしょう。
ファクタリングを活用した与信管理の注意点
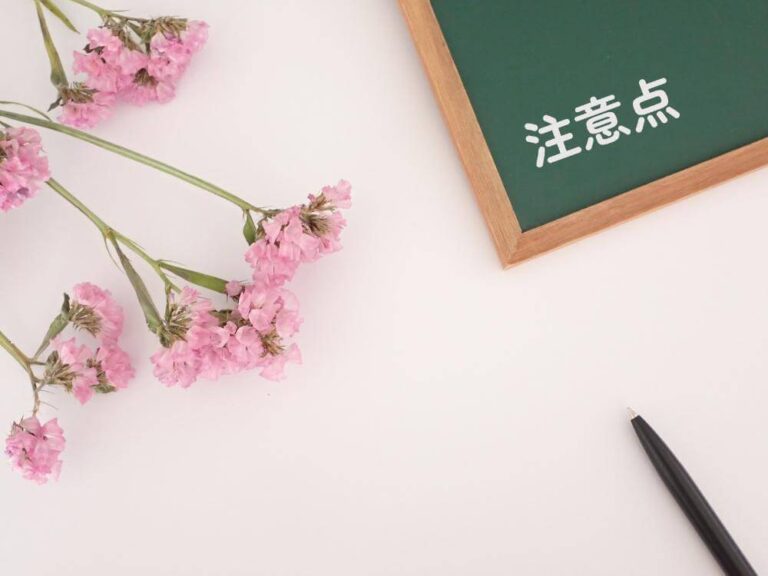
ファクタリングを活用した与信管理の注意点

新しい売掛先は信用度の評価が低くなりがち
ファクタリング会社が売掛先の信用力を評価する際には、過去の取引実績や財務データなどが重要な判断材料となります。そのため、設立間もない企業や、取引実績の乏しい新規の売掛先については、ファクタリング会社が十分な信用情報を得られず、評価が慎重になる(低くなる)傾向があります。結果として、ファクタリングの利用を断られたり、手数料が高く設定されたり、買取可能額が低くなったりする可能性があります。したがって、新しい取引先の与信判断の全てをファクタリング審査に頼るのではなく、自社でも可能な範囲で情報収集や評価を行うことが望ましいでしょう。
利用者の信用力も必要
ファクタリング審査の主軸は売掛先の信用力ですが、ファクタリングを利用する企業自身の信用力が全く問われないわけではありません。特に2社間ファクタリングの場合、売掛先からの入金を利用者が一旦受け取り、それをファクタリング会社に支払うという流れになるため、利用者がその入金を使い込んでしまうリスク(横領リスク)をファクタリング会社は懸念します。そのため、利用者の事業継続性や財務状況、経営者の信頼性なども、審査の過程で考慮されることがあります。利用者の信用状態が極端に悪い場合には、ファクタリングの利用が難しくなるケースもあり得ます。
手数料が発生する
ファクタリングは便利なサービスですが、利用にあたっては必ず手数料が発生します。手数料率は、売掛先の信用度、ファクタリングの種類(2社間か3社間か)、契約内容などによって異なりますが、一般的に銀行融資の金利よりも高くなる傾向があります。特に、2社間ファクタリングは3社間ファクタリングに比べて手数料が高めに設定されることが多いです。与信管理やリスク回避のメリットがあるとはいえ、手数料負担によって得られる資金額が目減りすることは避けられません。そのため、資金調達コストと、与信管理・リスク回避によって得られるメリットを比較衡量し、費用対効果を慎重に検討する必要があります。
売掛先の情報収集目的だけでは利用できない
ファクタリングの審査プロセスが売掛先の信用評価を含むからといって、純粋な信用調査や情報収集のためだけにファクタリングを利用することはできません。ファクタリングは、あくまで売掛債権を売却して資金化することを前提としたサービスです。ファクタリング会社も、買取を実行することで収益を得ています。したがって、「売掛先の信用度を知りたいだけなので、審査だけしてほしい」といった依頼は受け付けられません。ファクタリングを与信管理に活用するというのは、実際にファクタリング契約を結び、資金調達やリスク移転を行うという本来の目的の中で、副次的に信用情報を得る、という位置づけであることを理解しておく必要があります。
保証ファクタリングでは資金調達はできない
ファクタリングには、売掛債権を買い取る「買取ファクタリング」の他に、「保証ファクタリング」というサービスも存在します。保証ファクタリングは、売掛先が倒産した場合などに、ファクタリング会社が売掛金の回収を保証してくれる、一種の保険のようなサービスです。これにより貸倒れリスクを回避できますが、売掛債権の買取は行われないため、早期の資金調達効果はありません。与信管理の観点からは、貸倒れリスクのヘッジにはなりますが、買取ファクタリングのように「資金調達+与信管理」という一石二鳥の効果は得られません。目的に応じて、買取ファクタリングと保証ファクタリングを使い分ける、あるいは併用することを検討する必要があります。
一般的に与信管理をすべき適切なタイミングは?

ファクタリングの活用とは別に、そもそも企業が与信管理を行うべき適切なタイミングはいつでしょうか。まず最も重要なのは、新しい取引先と契約を結ぶ前です。相手の支払い能力や信用状態を事前に把握せずに取引を開始するのは非常にリスクが高いため、必ず与信調査を行い、与信限度額を設定すべきです。次に、既存の取引先に対しても、定期的な見直しが必要です。最低でも年に一度、決算期の後などに財務状況を確認し、信用状態に変化がないか、設定している与信限度額が適切かを確認します。加えて、取引先に関するネガティブな情報(業績悪化の噂、支払い遅延の発生など)を耳にした場合や、取引額を大幅に増やす場合なども、臨時に与信状況を確認すべきタイミングと言えます。
まとめ
ファクタリングは、売掛債権の早期資金化という主目的の他に、与信管理のツールとしても活用できる可能性を秘めています。ファクタリング会社の審査プロセスを通じて、売掛先の信用力を第三者の視点から評価してもらえる点や、ノンリコース契約であれば未回収リスクそのものを回避できる点が、与信管理上のメリットとなります。資金調達とリスク管理を同時に行える効率性も魅力です。しかし、手数料が発生すること、新しい取引先の評価が難しい場合があること、情報収集目的だけでは利用できないことなどの注意点も理解しておく必要があります。ファクタリングを与信管理に役立てる際は、その特性と限界を理解し、自社の与信管理体制を補完する手段の一つとして、賢く活用していくことが重要です。









